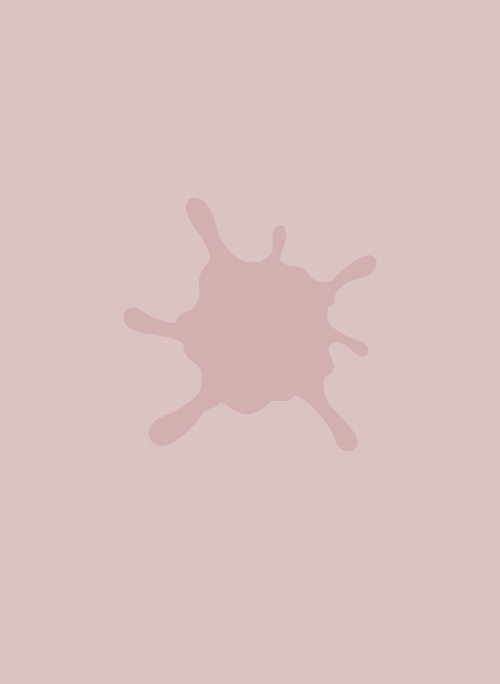―小話を一発―
カウベルを鳴らして輝くような美脚をした紅いハイヒールの女性がさっそうと入ってきた。
『待った?』
『いいや』
彼女はすっと目の前の席に座ると、長い脚を見せつけるように組んだ。
『コーヒー一つ』
彼女は首筋にかかった長い髪を背に流して言った。
* * *
ぽりぽりぽり。彼女は丹唇に鉛筆をくわえて、紙面に赤でチェックを入れてゆく。
「っあー! イマイチ、イマニよ」
僕は浅く腰掛けた座席から、姿勢を正した。
「いーい? ここはア……」
* * *
『ブルマン一つ。ああ、君の好みはカフェ・ラテだったね』
『遅くなったかしら』
『いいや、美人を待つのも楽しみのうちさ。今日の君の美しさも格別だね』
「で、男の寛容さと愛情、優しさ、気遣いを見せるのよ。わかる? ここは良い男って思わせなきゃ、読者つかない。釣れない。あと優しいだけもダメ。あくまでミステリアスに」
「は、はいっ、とメモメモ」
僕はいい女を書きたがる癖があるので、いつも長崎担当に叱られる。
もっと気障な男を書かなくちゃいけない。わかってるのに……僕、縁がないからなあ。
そんな僕は長崎担当に密かに(はあと)なのだが、いつまで経っても勝算はあがらない。
もう何度も聞かされた美しい声でがなり立てられる。
ああ、いい声だ。
いつぞやはきわどいのをもってって、エロでグロのナポレオン文庫かと怒られたっけ。
* * *
「ほんっとに! もう! うちはハーレクイン! 女性向けラヴ・ロマンスだって、わかってらっしゃるの? 全くもう! これじゃハードボイルドよ!」
と、言葉遣いは乱さず、鼻息を荒くして筋肉だるまのようなニューハーフの長崎担当はこちらを睨んだ。
僕、筋肉はスキなんだけど、もう一生この人とは縁がない気がするな。
だって、僕、女の子だから相手にされてない気がする……
END
カウベルを鳴らして輝くような美脚をした紅いハイヒールの女性がさっそうと入ってきた。
『待った?』
『いいや』
彼女はすっと目の前の席に座ると、長い脚を見せつけるように組んだ。
『コーヒー一つ』
彼女は首筋にかかった長い髪を背に流して言った。
* * *
ぽりぽりぽり。彼女は丹唇に鉛筆をくわえて、紙面に赤でチェックを入れてゆく。
「っあー! イマイチ、イマニよ」
僕は浅く腰掛けた座席から、姿勢を正した。
「いーい? ここはア……」
* * *
『ブルマン一つ。ああ、君の好みはカフェ・ラテだったね』
『遅くなったかしら』
『いいや、美人を待つのも楽しみのうちさ。今日の君の美しさも格別だね』
「で、男の寛容さと愛情、優しさ、気遣いを見せるのよ。わかる? ここは良い男って思わせなきゃ、読者つかない。釣れない。あと優しいだけもダメ。あくまでミステリアスに」
「は、はいっ、とメモメモ」
僕はいい女を書きたがる癖があるので、いつも長崎担当に叱られる。
もっと気障な男を書かなくちゃいけない。わかってるのに……僕、縁がないからなあ。
そんな僕は長崎担当に密かに(はあと)なのだが、いつまで経っても勝算はあがらない。
もう何度も聞かされた美しい声でがなり立てられる。
ああ、いい声だ。
いつぞやはきわどいのをもってって、エロでグロのナポレオン文庫かと怒られたっけ。
* * *
「ほんっとに! もう! うちはハーレクイン! 女性向けラヴ・ロマンスだって、わかってらっしゃるの? 全くもう! これじゃハードボイルドよ!」
と、言葉遣いは乱さず、鼻息を荒くして筋肉だるまのようなニューハーフの長崎担当はこちらを睨んだ。
僕、筋肉はスキなんだけど、もう一生この人とは縁がない気がするな。
だって、僕、女の子だから相手にされてない気がする……
END