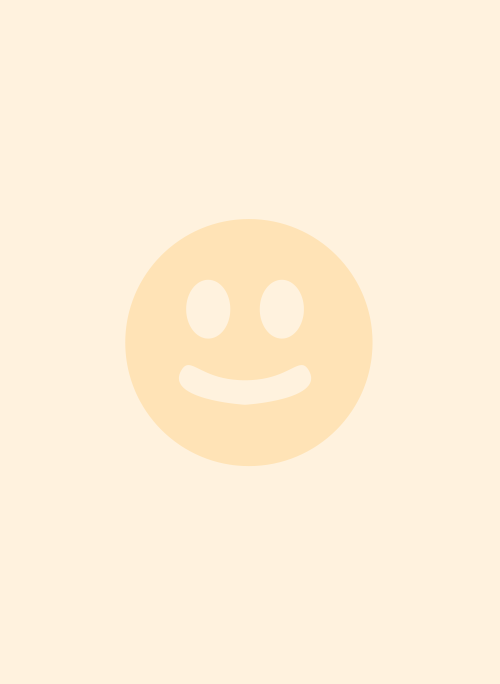飛び起きると嫌な汗をかいていた。 記憶が戻らない事で不安に感じているからだろうか、それとも現実に起きた出来事なのだろうか、思い出せない事が腹立たしかった。
「体調はどうですか?」
依然と変わらず…なぜそう思ったのだろうか、奇妙な疑問を抱きつつも彼女のに場所を聞いた。
「ここはどこなんです?」
「診療所…よ」
「病院ですか?」
「医者はいないの、だから看護婦…今は看護師ね、看護師の私が簡単な治療を行っているんです」
「はぁ…」
なぜかそのことが異質な事に思えた。それでも命を救ってくれたのは確かだから礼を述べた。
「助けて頂いて、ありがとうございます」
「…」
その言葉を聞いた彼女は意味深な笑みを浮かべてこう言った。
「いえ、お大事に…」
何かが引っかかる。思い過ごしと言えばそれまでなのかも知れない、現に先ほどの笑みは女性らしく素敵なものだったし、その言葉にはなんの意図があるとも思えないから、それでも戻らない記憶の為か不安は拭えなかった。
「体調はどうですか?」
依然と変わらず…なぜそう思ったのだろうか、奇妙な疑問を抱きつつも彼女のに場所を聞いた。
「ここはどこなんです?」
「診療所…よ」
「病院ですか?」
「医者はいないの、だから看護婦…今は看護師ね、看護師の私が簡単な治療を行っているんです」
「はぁ…」
なぜかそのことが異質な事に思えた。それでも命を救ってくれたのは確かだから礼を述べた。
「助けて頂いて、ありがとうございます」
「…」
その言葉を聞いた彼女は意味深な笑みを浮かべてこう言った。
「いえ、お大事に…」
何かが引っかかる。思い過ごしと言えばそれまでなのかも知れない、現に先ほどの笑みは女性らしく素敵なものだったし、その言葉にはなんの意図があるとも思えないから、それでも戻らない記憶の為か不安は拭えなかった。