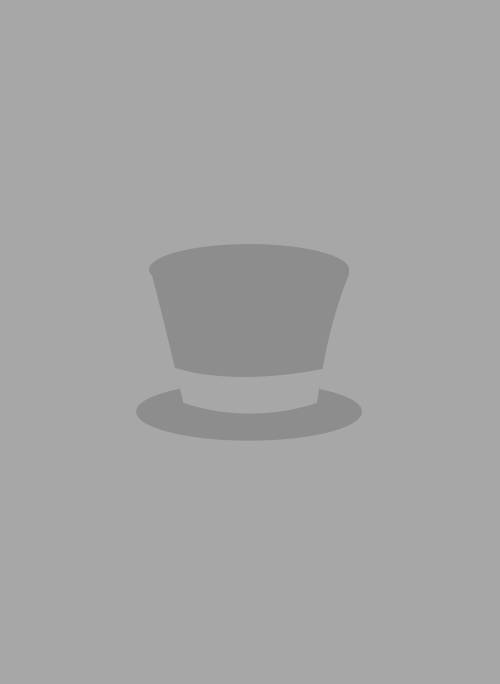「…」
鏡の中の自分をじっと見つめる。
でも、見つめ返してくる女は変わらない私。
よく見るとおでこのところが少しカサカサしているが、それは単なる乾燥にすぎない。
冬の湿度の低さを甘く見ていた私がわるい。
蛇口を捻ると痛いくらいに冷たい水が、勢いよく流れ出た。
両手ですくって顔を乱雑に洗う。
もう一度鏡を見ても、やっぱりそこには変わらない私だけだった。
なんにも、変わってない。
私は。
店長の言葉で、ゼンのことを思い出した。
あの夜以来、自分のことが日に日によくわからなくなってきている。
考えなきゃいけないことは、たくさんあるはずなのに、何だか思い出せない。
いや、
・・・・・・・・
思いださないように、ストッパーが掛けられているみたい。
でも、何に…――?
ズキンッ
「ぁっ…」
突然、酷い頭痛に襲われる。
こめかみ辺りにまるで鈍器で殴られたような激痛がはしった。
なに、コレ…?
私はへなへなと崩れ落ちる。
全身からぶわりと嫌な汗が吹き出す。
まだ濡れている髪からぽたぽたと水滴が垂れて、肩や胸に落ちた。
そのたびにぞくり、と背筋を何かが這うような悪寒がした。
痛い。
なんで?!
「ゼン…」
こんなときに、真っ先に頭に浮かぶのは、あのキレイな男。
馬鹿だよ、シノ。
アイツは手に入るような男じゃないんだよ。
なのに、霞む頭で響くのは、ただ一人の名前。
なんて、憐れなの。
痛い、
頭が、割れそうだ。
痛い、痛い!!!
「ゼン…っ」
そして私は意識を手放した。