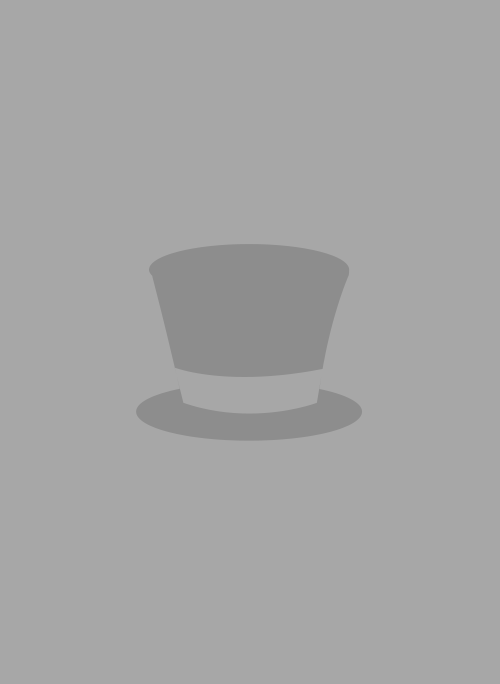「…私が……ッチ…消した」
「チ…?」
「だって…お母さんがっ!……消してって…!」
「…チ?なんだよそれ」
「白い…機械、の……」
唇をかみしめて、顔をぐちゃぐちゃに歪ませた志乃は、そう言った。
白い機械の、スイッチ。
「…っ嘘だろ……」
まさか、本当に?
青ざめる、とはまさにこういうことだろう。
一瞬で体温が下がった気がした。
スイッチとは、きっと呼吸を助ける機械とか、そういうもののスイッチのことだ。
彼女の母親は治らない病だった。
寝たきりで、そのせいの苛立ちを彼女にぶつけていたのだ。
治らない身体。
募る、虚しさ。
志乃が店で働き始めたのも母親の入院費を稼ぐためだった。
でなければ、彼女はとっくに死んでいたことだろう。
なのに。
それ、なのに。
そんな母親が、スイッチを…自分の、命の綱を消せだと?
泣きじゃくる志乃の話を要約すると、彼女は俺の言いつけどおり部屋から出なかったらしい。
ところが母親から電話がきた。
今から来てほしい、という内容の。
もちろん志乃は断ったが、何度もかかってくるのだ。
何度も何度も。
そのたびに内容は段々とエスカレートしてくる。
見かねた彼女は病室まで足を運んだのだろう。
そこで、母親に頼まれた…と。
「お母さん…もう生きてるのが辛いっ…て。もういやって……」
嘘だと、言ってほしい。
言えよ、志乃。
だって、そんなの酷すぎる。
「私…納得、して!!」
そんな自分が、汚い。
まるでそう言うように、彼女は吐き捨てた。