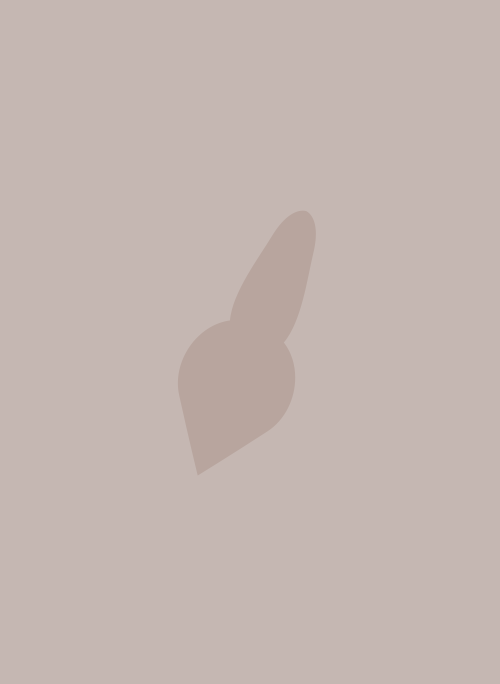一人。私は一人。
この声が、顔が、存在がなければ。
私は一人じゃなかっただろうか。
「それが聞いて驚きなよ、この女の子、なんと丑松の知り合いなんだって!」
「京に来てまだ数日しか経ってないのにもう知り合いを作ったのかい? しかもこんな美人さんだ。髪もすごくきれいじゃないか」
「でも辛そうだね。涙の跡がある」
「丑松、あんた泣かしたんじゃないだろうね?」
「俺そんなことしてないし。て言うか腹減った絹松。なんか食べたいもしくは寝たい」
沢山の声が聞こえると思って目を開けたら、私は沢山の人に囲まれていた。驚いて後ずさろうとするけれど、後ろにも人がいる。知っている顔はあの少年ぐらいだ。
「落ち着きなさい、椿ちゃん」
「あの、私」
「あたいは草苅絹松だ。よろしくね」
ここはどこでわたしはなにを。
「驚くのも無理はないよ。丑松が勝手に島原まで運んだんだ。アンタが――空き旅館で倒れているところをね。しかも剥き身の小刀近くにおいて、泣いていたらしいじゃないか」
「――わたし」
「死のうとしていたのかい?」
絹松さんが私の目をじっと見てくる。私は居たたまれなくなって俯いた。すると彼女は大きなため息を吐いてずいっと私に寄ってきた。そして私の頬を両手でつねり始める。
「いひゃ」
「中村椿は江戸じゃ有名だったよ。だから私にはアンタの言わんとしてる事は分かる。その美しい声に、可愛い顔に、みんな嫉妬してあんたを殺そうとしてくるんだろ? あんたはそれが怖くて死にたかったんだろ?」
その通りだ。私はそれのせいで沢山のものを失ってしまった。最早自分の意志でさえあるのか分からないぐらいだ。だから私は死のうとした。だけど彼女は私の頬をつねるだけ。そして私をじっと見るだけ。
「私が怖い?」
「ほわいえふ」
「ん?」
「離してやれよ絹松、喋れてない」
「あぁ、ごめんね」
手が離されてひりひりする頬を撫でながら私は少年を見た。彼は落ち着いた様子で絹松さんと私を見比べている。それになんの意味があるかは分からないけれど。
「それで?」
「――こわいです」
「うん。だけど私はあんたよりキレイだ。声は酒焼けでがらついているし、肌も傷だらけであんた程すべすべではないけれど。私はあんたよりいい女だって胸を張れるよ。それでもあんたは、私の事が怖いのかい?」
絹松さんの言葉の意図はあまりよく分からなかった。だけど、その笑顔を見た途端に彼女の事は――いいや。この場にいる人がみんな怖くなくなった。私は殺されない。
あまりの感動に私は絹松さんの手を取って頭を下げた。この人はすごい女の人だ。