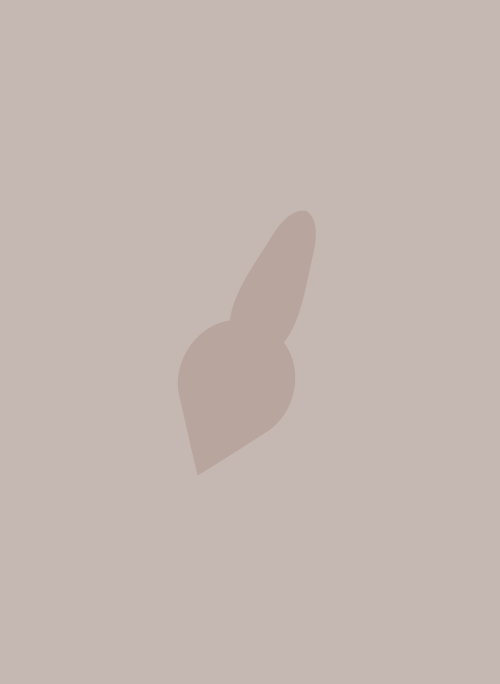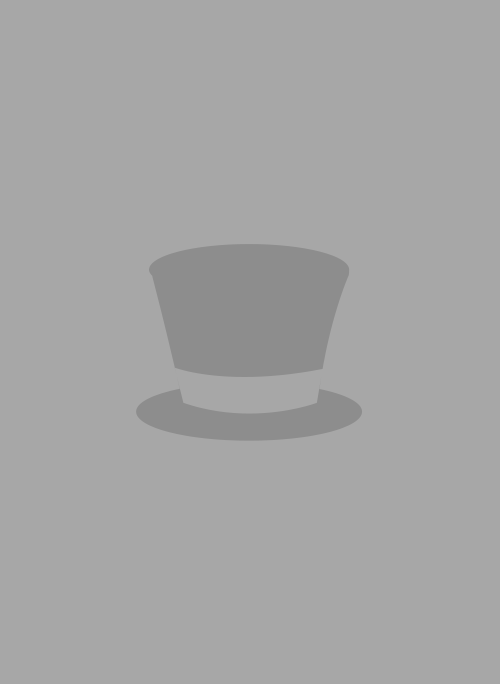「逃げろ」
「え?」
「お前は居場所を手に入れたんじゃない。主に支配されただけだ。狙われないんじゃなくて逃げられなくなっただけだ、椿」
ぐっと手を引いて、彼は私を旅館から連れ出そうとする。だけど私は首を振った。
「どうしてそんな事を言うんですか? 貴方は慶喜さまの忍、もし私があの御方に捕らえられる様な形になったとしても……私を逃がそうなどとしてはいけない人でしょう」
「お前は初めて俺を頼りにした奴だ」
「と、言うと?」
「京まで連れて行けと頼んだろ。俺は連れて行かなかったがお前は俺を頼った。ただそれが嬉しかったんだ。だから俺は椿を助けたい。このままじゃお前は」
殺される。
彼はそう言って私の手を離した。
「待って! 半助さん!」
そして何かを嗅ぎ付けた様に、急いで何処かへ消えてしまった。私は急に取り残されて考えることが出来なくなってしまう。殺されるなんていつもの事なのに。安心を一度でも一瞬でも覚えたらこうなるのか。
足音が聞こえた。誰かが花簪の開け放たれた戸を覗く。私は身構えて立ち尽くした。
「――椿?」
「……あなたは」
そこに現れた少年は、いつか江戸の吉原で会ったあの野望に満ちた少年だった。彼は泣きそうになりながら微笑むと、それとは逆に安心した様なため息を漏らした。私は唖然としたまま彼をじっと見る事しか出来ない。
「声がしたから、来たんだ」
「覚えて、たんですね。私の声を」
「忘れないよ。言ったろ、探すって」
しかしまあ、それがこんな早くに会えるとは思ってなかった。彼を苦笑いをして勝手に入ってすぐの段差に腰を下ろす。ぼろい着物は私とそう変わらないけれど、彼の方には幾つか血の跡がついている様だった。
「あの時はありがとう。お陰で俺の生きる道が掴めたよ。もう死に急ぐことも生き迷う事もない。本当に椿のお陰。ありがとう」
「いえ。ご無事で何よりです」
「簪なんだけど、もう少しだけ預からせてくれる? 情けないことに俺はまだ自分の名前がないから名乗れないんだよ」
「構いません。いつでも」
「俺は島原に住むことになったんだ。自警団に入って誰も死なないようにしようと思ってる。椿は、ずっとここにいるの?」
彼の瞳はもう野望には燃えていなかった。希望に輝いている。だけど私はどうだろうか。私の目には今何があるのだろうか。
人に任せっ放しで生きてきた。誰からも反感を買わないように容姿も声も出来る限りしか使わないで生きようと思ってきた。だけどそんな事は出来なくて、人から見たら恵まれてる声と容姿は邪魔でしかなかった。
私は美しさなんて要らないし、きれいな声も欲しくない。私が欲しいのはただ一つ。文句を言っても怒られない人間性。そんなもの手に入らないのは十二分に分かってるけど。
「椿」
「あ、はい。ごめんなさい。何ですか?」
「おいで。こっち。俺の家に行こう」
半助さんみたいに手首を持たれたけれど、私はその手をそっとほどいた。いけない。家になんて行ったら私は――彼の家族に殺されてしまうかもしれない。この姿と声で。
私は歯を喰い縛って首を振った。
「掃除が、ありますから」