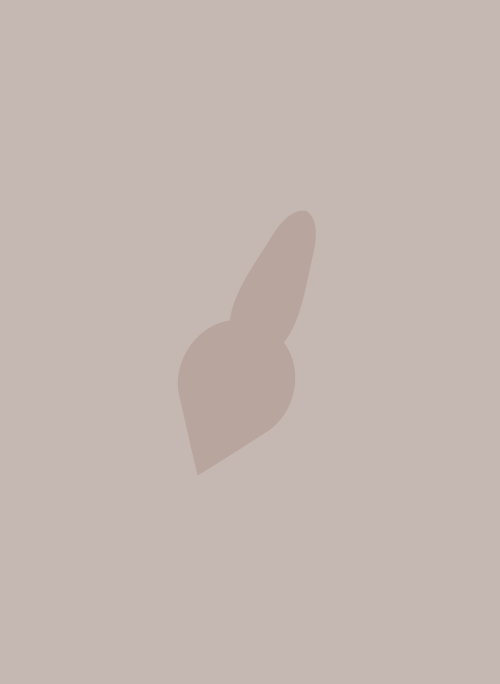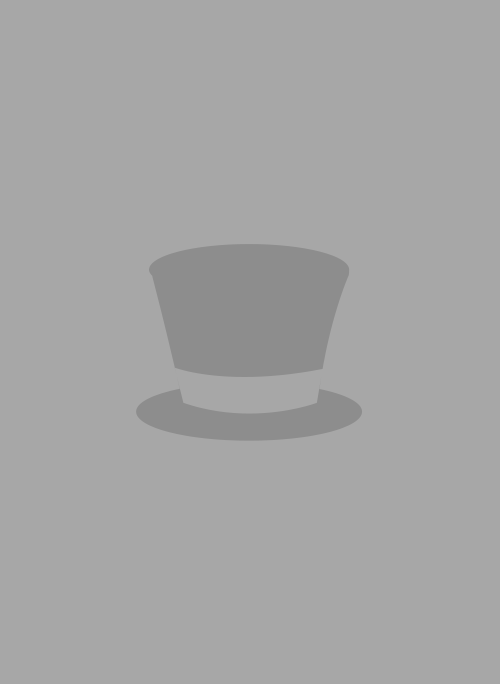「大変失礼を致しました。私とした事が、貴方様のお声に気付かないなんて――とんだご無礼を。お許しくださいませ、徳川慶喜様」
お顔はなんとなく知っていた。だが実際会うまでは、近付かれるまでは全く分からなかった。だがこの人はそうだ。徳川家の若き将軍だ。間違いない。
私は生唾を飲んで事態を理解した。
「顔を上げなさいと、俺言ったよ、椿」
その低い声に私は顔を上げる。彼は笑顔だった。だがその声は笑っていなかった。どの大人よりも怖かった。私を殺そうとした人より、私を騙して京へ飛ばした人よりも。慶喜さまの怖さは格が違う気がしてならない。
「力を貸してあげよう。椿、お前は今日からここで世話になるのだろう。ならこの旅館はお前のものだよ。精進して働きなさい」
「――え?」
「規格外の若女将誕生だな。元々ここは空き旅館だ。誰が使おうと文句は言わせまい。ここでお前が商売を始める事を許しやる。ただし、一つ条件がある。聞いてくれるか?」
私は力強く頷いた。
「うむ。まあ簡単な事だ。ここに私が来る事を承知して欲しい。この椿の間に私は休息を取りにたまに訪れたいと思う事があってな」
「――勿論で御座います。この旅館を私に、任せていただけるのであれば……それ程の幸せを私に与えて下さるのならば、お好きな時にどうぞ御越しくださいませ。出来る限りのおもてなしをさせていただきます」
慶喜さまは微笑んで立ち上がった。私は顔を上げたまま視線で彼を追いかける。ふと半助さんが私を見ているのが分かって彼と目線を交わした。今にも何か言いたげな顔だ。だが彼から言葉が出ることはなかった。
「さて、この館の主も決まった事だ。私も自分の屋敷に戻ろうかな。椿、今度私が来る時は生まれ変わった花簪を期待しているよ」
「お任せ下さい」
「うむ。行くぞ半助」
「御意」
彼らは窓から町へ消えて行ってしまった。残された私は息をゆっくりと吐いて笑った。とんだ計算違いだとは言え、私は自分の家を手に入れた。将軍お墨付きの屋敷だ。
これが喜ばずにいられるだろうか!
「あぁ、掃除しなければ!」
私の家を。私だけの家を!
立ち上がって階段をかけおりて私は厨房から汚れた布を引っ張ってきた。まだ何かを買う金がない。その布をもって川まで走り、綺麗にしてから戻ってくる。まずは番台。
玄関を綺麗に拭くまでに川まで何度も往復した。汚れた着物を振り乱して走る姿はさぞ滑稽だったに違いない。だけど私は幸せだった。私の家は私が規則。誰も私を殺せない。それが嬉しくて仕方なかった。
「椿」
ふと声がして、私は玄関を見た。戸の前に誰かが立っている。私は急いで戸を開けた。
「半助さん」
「さっきはごめん。お前を殺そうとした」
「あ」
「主の命令だ。他意はない」
「いいんです。殺されかけるのは慣れてますから。それより半助さんは慶喜さまのお忍だったのですね。驚きました」
「うん」
「そうだ、お茶を入れます半助さん。旅館は人をおもてなす場所ですから。どうぞ」
「違う、椿」
彼は厨房へ向かおうとする私の手首を持った。