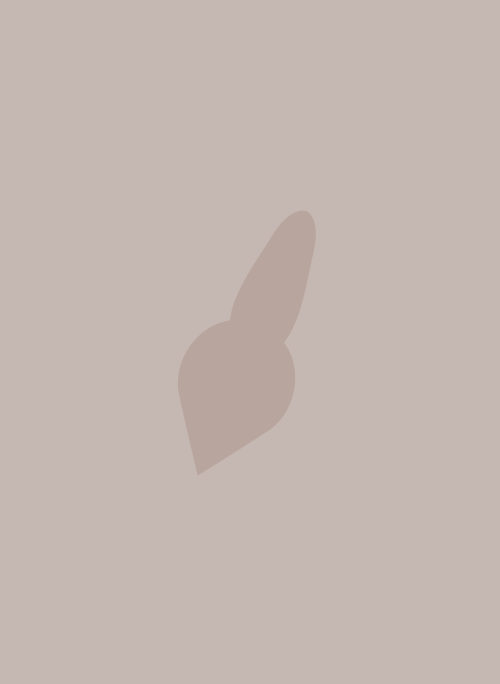馬鹿息子と呼ばれた吉原は少しだけ俺の顔色を伺った。だがすぐ華宮に背中を押されて追い出される。開いた襖がすぱんと音を立てて再び閉じられた時、華宮は。
華宮は泣いていた。
「お、おい」
「一度しか言わないからちゃんとお聞きになって。大和屋の旦那」
「あ、あぁ」
華宮は俺の着流しを取って俺の方へゆっくりと歩んだ。俺はその間の言葉を決して忘れない。華宮の命を懸けた様な、その言葉を。
そうして言い切った彼女は着流しを俺に渡すついでに俺の胸へ飛び込む様に倒れ、その襟をぎゅっと握り締めてこう呟いた。
「私なんかの為に、あんなに良い人を時代に殺させる訳にはいかない。どうか村崎殿を止めておくれよ旦那。どうか、お願いだ」
――。
多分、村崎はそう言う死に方をするのだろうなとは思っていた。あれは根っから悪を嫌っているしそれ以上に人助けをしたがる。
だから寿命を全うして孫に囲まれて幸せに死ぬのは無理だと思っていたんだ。随分、昔から。
だが。
「離せ華宮」
「旦那」
「俺に出来るなら何とかする。村崎を死なせる訳にはいかないからな。だが俺は口で村崎に勝てた覚えがないから保証はしかねる」
「あぁ、ありがとう」
「吉原には言うなよ」
俺はため息をついて着流しを羽織ると、窓際に座り込んだ。太陽が眩しい。島原は寝ているのに俺はこれからきっと眠れない。
目を閉じて腕を組むと少しだけ落ち着いた。そこで初めて、自分が落ち着いてなかった事を知る。
「俺は村崎が嫌いなんだ」
「旦那?」
「両親も祖父母も健在で、剣術の才能もあった。将来は代々の職である徳川の側近を継ぐ男だった」
「そんな、お方なのかい」