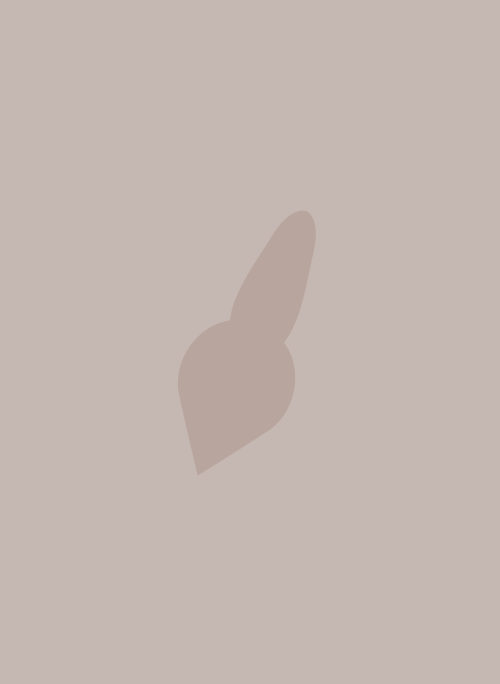「なんですって?」
「人に言えない紅椿。それを知ってる私にも言えない事となれば、それぐらいしか思い付かないよ」
怖がる訳でも逃げる訳でも、抵抗する訳でもなく。華宮太夫は俺を見据えて笑顔を浮かべている。
大人。これが大人?
「沖田さん」
「アンタが出来ないなら俺がやりますよ、瀬川の兄さん。残念だけど――悩む時間はないんでね」
新撰組はきっと来る。なら早く済ませて夜が来る前に逃げた方が頭が良いってものじゃないか。
土方さんが時間を稼いだとしても、夜には昼以上の首代が動く。やはり善は急げ。否、善じゃないけれど急がなければいけない。
「本気ですか、丑松殿を敵に回す事になるんですよ。露見を恐れる紅椿がそんな事で良いんですか」
「俺と土方さん二人に直々の命が下ったんです。本気じゃなきゃ来ませんよ。それに吉原の旦那は紅椿を露見したりしない。あの人は大和屋の旦那が気に入ってるし」
殺すなら俺だけを殺すはず。
「しかし沖田さん」
「無駄話は時間の無駄です。死を前に恐怖する人の事も考えなきゃいけませんよ瀬川の兄さん」
とは言ったが、華宮太夫は恐れていない。何を考えてるのかも分からない。俺が餓鬼だからか?
なぜ怖がらないんだろう。
「丑松殿は華宮さんを殺した人を許しませんよ。新撰組がどうなるか、あなたがどうなるか――」
「新撰組には土方さんがいる。俺は死んだって構わない。だって、俺が消えても何も変わらない。そうでしょう。それに俺は吉原の旦那と仕合ってもみたいしね」
自分がこんなに饒舌になる様は久しぶりかも知れない。俺はそんなに焦っているのだろうか。命をこなすだけなのに。いつもと何ら変わりはないと言うのに。
「沖田さん」
「瀬川さん、責めるのはよしてあげなよ。私の事は構わない。こんな商売してるんだ。恨みだって買う覚悟はちゃんてあるから」
「――違います、華宮さん」
兄さんは言う。
「沖田さんはお幾つですか?」