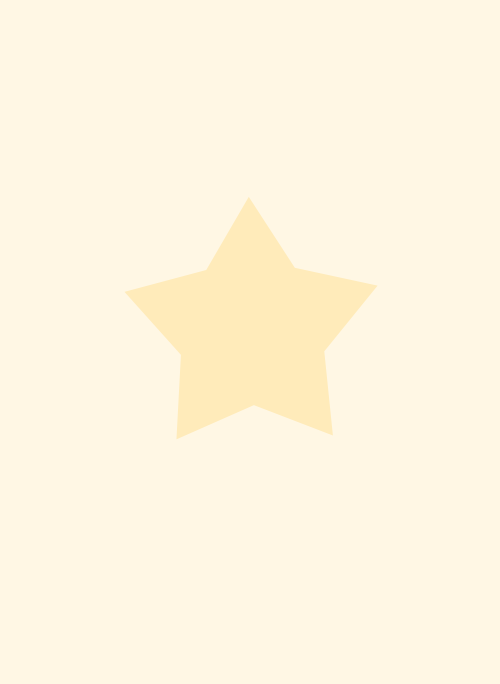連れられて行った先は、泥臭い人権派弁護士の彼には似つかわしくない、格式高そうなフレンチレストランで。
テーブルに着く時、椅子を引かれた時には身構えた。
育ちの貧しいあたしには、全く馴染みのない雰囲気で、肩が凝るったら……
対する彼は、メニューを広げ、何やら給仕と言葉を交わしている。
――もしかして、こういう場に慣れてる?
あたしの頭には、?の疑問符が飛び交っていた。
いつもあたしの家の狭いダイニングキッチンで、子供達と肩を並べ、ハンバーグを頬張る彼の姿と、どうにもこうにも重ならない。
周りを見渡すと、ここはどうやら、かなりハイレベルのレストランのようだ。
何より、お客の身なりが半端ない。
中にはカクテルドレス紛いの豪華な装いのご婦人までいる。
思わずゴクリと生唾を飲み込んだ。
――場違いなのは、あたし?
そんなあたしの目の前に、すらりと伸びた美しいフロートグラスが、すぅっと置かれた。