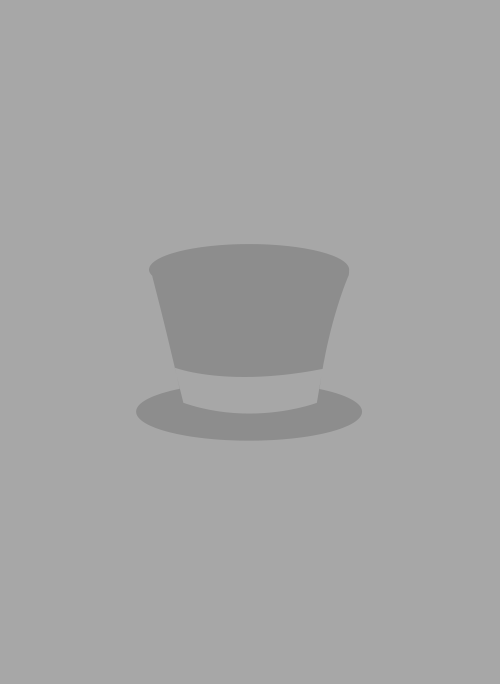生きている訳でもなく死んでいる訳でもない。中途半端なこの体で人前に出る事など、不可能である。このまま、自分の肉体が、完全に朽ち果てるまで、この状況は続くのだ。彼は、神様や悪魔の事を改めて恨んだ。ナゼ、死んだままにしておいてくれないのか…。
「ジョン、おいでー」
朝の爽やかさに混じって少女の声が墓地に響き渡る。彼はその方向に視線を移し、じっとその様子を伺った。
その声の感じから、少女は5~6歳位と思われた。
彼は狼狽した。変わり果てた自分の姿を見られたくなかったからだ。生きる者とはかけ離れた今の自分の姿は少女に嫌悪感を与えるだけであろう。咄嗟にそう思って自分の身を隠すべき所を探したが、広い墓地の中には身を隠すべきところなど見当たらなかった。
「ジョン?何処言ったの、ジョン?」
彼女は一緒に連れていた犬を探しているのであろうか、整然と並んだ墓石の間を縫う様にその声は段々と自分に向かって近付いて来る。
「ジョンってば、もうお散歩はおしまい、帰ろうよ!、ジョ…」
少女の視線と彼の視線が絡み合う。下草がはらりと風に揺れ、萌える緑の香りが匂う。
彼は少女に自分の姿を見られてしまったのだ。異様な風体の自分を見た彼女の反応など、火を見るよりも明らかだ。彼女は泣き叫びながら、両親の元に返り、自分の事を言いつけるだろう。その事を両親が本気にするかどうかは別として、少なくとも少女の心には、何等かのキズを残すに違いない。
彼はきしむ体でゆっくりと立ち上がり、その場を立ち去ろうとした、が、その瞬間、彼女と視線がかち合ってしまった。そしてふたりはそのまま固まる…
先に正気に戻ったのは彼だった。彼は少女の次の行動を予測した。そう、泣き叫びながらこの場から逃げていくと言う予測を。
「ジョン、おいでー」
朝の爽やかさに混じって少女の声が墓地に響き渡る。彼はその方向に視線を移し、じっとその様子を伺った。
その声の感じから、少女は5~6歳位と思われた。
彼は狼狽した。変わり果てた自分の姿を見られたくなかったからだ。生きる者とはかけ離れた今の自分の姿は少女に嫌悪感を与えるだけであろう。咄嗟にそう思って自分の身を隠すべき所を探したが、広い墓地の中には身を隠すべきところなど見当たらなかった。
「ジョン?何処言ったの、ジョン?」
彼女は一緒に連れていた犬を探しているのであろうか、整然と並んだ墓石の間を縫う様にその声は段々と自分に向かって近付いて来る。
「ジョンってば、もうお散歩はおしまい、帰ろうよ!、ジョ…」
少女の視線と彼の視線が絡み合う。下草がはらりと風に揺れ、萌える緑の香りが匂う。
彼は少女に自分の姿を見られてしまったのだ。異様な風体の自分を見た彼女の反応など、火を見るよりも明らかだ。彼女は泣き叫びながら、両親の元に返り、自分の事を言いつけるだろう。その事を両親が本気にするかどうかは別として、少なくとも少女の心には、何等かのキズを残すに違いない。
彼はきしむ体でゆっくりと立ち上がり、その場を立ち去ろうとした、が、その瞬間、彼女と視線がかち合ってしまった。そしてふたりはそのまま固まる…
先に正気に戻ったのは彼だった。彼は少女の次の行動を予測した。そう、泣き叫びながらこの場から逃げていくと言う予測を。