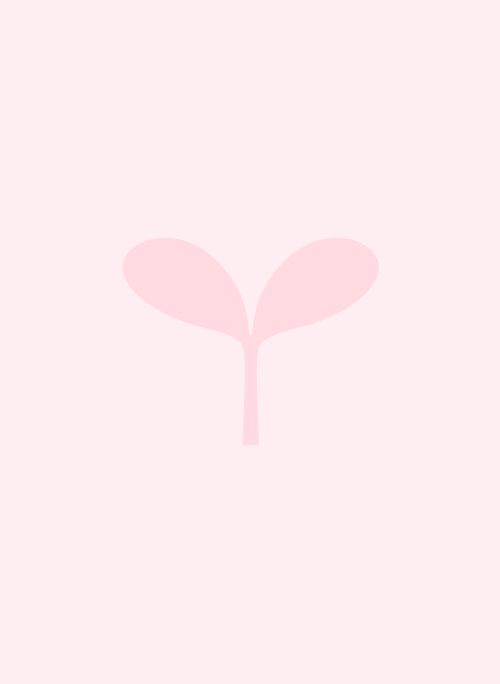ふいに優しく頭に手が置かれた。
チラッと見るとオーナーが微笑んでいた。
これでタバコ吸ってなかったらもっと良かったのに。
「感謝してんなら迷惑とか簡単に言うもんじゃねぇ。 分かったか?」
「・・・ハイ。 すみませんでした」
そういったと同時に、わしゃわしゃっと乱暴に頭をなでられる。
本当は髪がグシャグシャになるからこのなでられ方は嫌いだ。
でも、今は嫌いじゃない。
オーナーが許してくれている気がしたから。
「あぁ、ほら 蒸しタオル目に当てとけ」
「ちょ、これどっから出したんですか?! ってか熱っ!!!」
「んなもん奥からに決まってんだろうが」
「・・用意周到なことで」
皮肉交じりにいってみるが、オーナーは全く気にしていないご様子。
あぁ、くやしい。
「それから、泣きながら睨んでも全く威嚇になんかなってないからな むしろ襲ってくれっていってるようなもんだぞ?」
「なっ!! 何言ってんですか!? 私、そんなことこれっぽっちも思ってませんから」
「大丈夫だ。 年下を襲うような趣味は生憎、持ち合わせていないんでね」
「持ってなくて結構です!!」
少しだけ頬を赤く染めながら、私はそれなりに冷めてきた蒸しタオルを目に置く。
・・・気持ちいい。
こういうことには敏感なんだ、このオーナーは。
「さて、そろそろほかの客も来る頃だ 準備しておけよ」
「・・・はい」
私は蒸しタオルをカウンターに置いて立ち上がった。
チラッと見るとオーナーが微笑んでいた。
これでタバコ吸ってなかったらもっと良かったのに。
「感謝してんなら迷惑とか簡単に言うもんじゃねぇ。 分かったか?」
「・・・ハイ。 すみませんでした」
そういったと同時に、わしゃわしゃっと乱暴に頭をなでられる。
本当は髪がグシャグシャになるからこのなでられ方は嫌いだ。
でも、今は嫌いじゃない。
オーナーが許してくれている気がしたから。
「あぁ、ほら 蒸しタオル目に当てとけ」
「ちょ、これどっから出したんですか?! ってか熱っ!!!」
「んなもん奥からに決まってんだろうが」
「・・用意周到なことで」
皮肉交じりにいってみるが、オーナーは全く気にしていないご様子。
あぁ、くやしい。
「それから、泣きながら睨んでも全く威嚇になんかなってないからな むしろ襲ってくれっていってるようなもんだぞ?」
「なっ!! 何言ってんですか!? 私、そんなことこれっぽっちも思ってませんから」
「大丈夫だ。 年下を襲うような趣味は生憎、持ち合わせていないんでね」
「持ってなくて結構です!!」
少しだけ頬を赤く染めながら、私はそれなりに冷めてきた蒸しタオルを目に置く。
・・・気持ちいい。
こういうことには敏感なんだ、このオーナーは。
「さて、そろそろほかの客も来る頃だ 準備しておけよ」
「・・・はい」
私は蒸しタオルをカウンターに置いて立ち上がった。