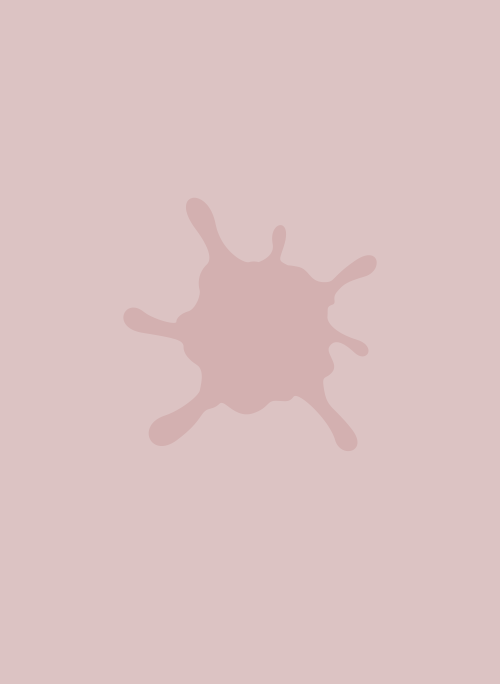ただ、朝の少女が呆然とした表情で俺を見ていたのが印象に残った。
そうか、俺は最初から彼女が崎浜高校の生徒だと分かっていたけど、彼女の方からすれば、今の今まで知らなかったのだから。
「ありがとうございます、藤島先生」
ふと、近くで聞こえた聞き間違えようのない一目惚れの相手の声に、想わず勢いよく振り返る。
案の定、生徒会長の内海七緒が、ふわりと微笑んだまま背後に立っていた。
まずい、思ったが時既に遅く、ぶわっと頬に熱が集まる。
ぐ、と顔に力を入れてできるだけポーカーフェイスに努める。
表情を作ることは割と得意だ。
だから、今回も周りをごまかすのは容易だと、思っていたのに。
視線を感じて振り向いた先には、朝の少女――後に名前を知ることになる、本庄青葉がいた。
自分でも、どうしてこんなことをしたのだろうと思う。
内海のことはもう諦めるはずだったのに。
気づいたら、本庄を壁際に追い詰めて協力を仰いでいた。
しかも、半ば強制的に。
本気で内海に俺のことを意識してほしいとは思っていない。
来年になれば、内海も卒業するだろうが、それまでに彼女をどうこうできる勇気なんてあるはずもない。
ただ、何となく、本庄と話がしたかっただけなのかもしれない。
あの、ネックレスを渡したときの彼女の表情が、どうしても忘れられなかったから。