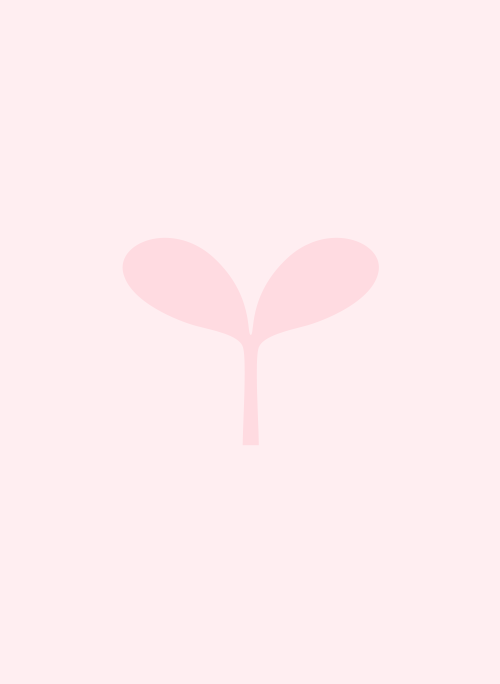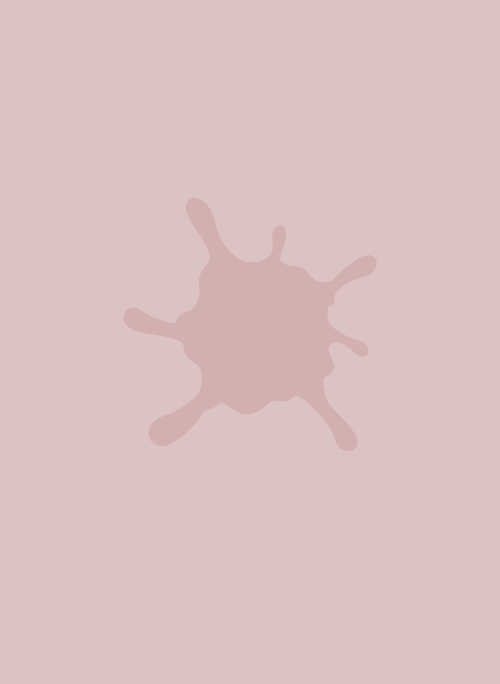見慣れた田舎の風景だった。
藁葺き屋根の家がぽつぽつと散らばり、小さな田んぼが家と家の間でたわわに稲を実らせる。
稲穂をゆらす風が少し冷たくなってくる。
夕暮れ時になると、私は道端の木陰に座って彼女を待つのだった。
彼女が私の前に姿を現すのは、決まって日が沈んだあと辺りが薄暗くなってからだ。
彼女は私と同じ人間ではなかった。
私が生まれるずっと以前からこの村に住んでいる、妖怪だった。
藁葺き屋根の家がぽつぽつと散らばり、小さな田んぼが家と家の間でたわわに稲を実らせる。
稲穂をゆらす風が少し冷たくなってくる。
夕暮れ時になると、私は道端の木陰に座って彼女を待つのだった。
彼女が私の前に姿を現すのは、決まって日が沈んだあと辺りが薄暗くなってからだ。
彼女は私と同じ人間ではなかった。
私が生まれるずっと以前からこの村に住んでいる、妖怪だった。