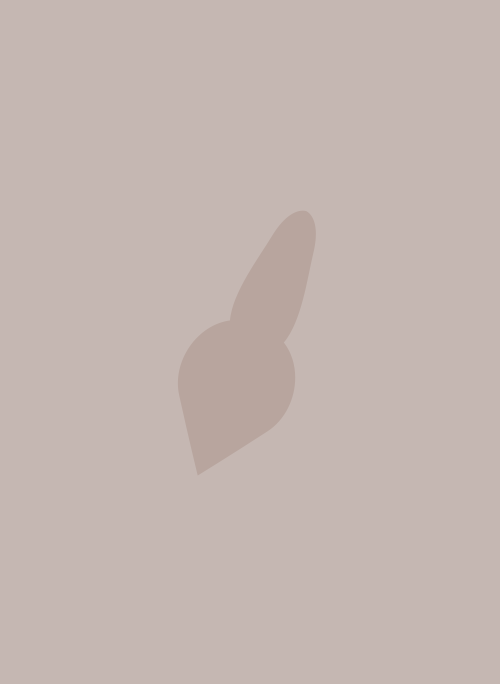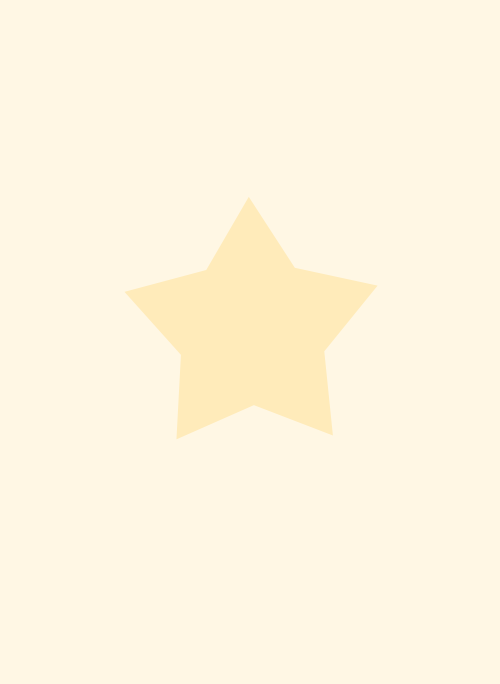「で? アザムは医者に?」
「え……いえ、父親としてまだまだなのでしょうかね? アザムの思考が最近ちょっと分りかねていて……」
自信なさげに答えるレイの姿がそこにはあった。
ベリルは六年前、“お医者さん”になりたいとアザムから聞いていたため、不思議がり眉をひそめた。
レイは医者でありアザムは医者の子どもとなったのだから、そこへ進んでもおかしくは無い。
「医学書などを読んだりしてますし、数学、化学関係で分らない事は、尋ねられるのですが……何かを悩んでいるような感じで」
「直接訊いてみたら良いのでは?」
「……いえ、これは自分から話すまで、訊べきでは無い気がするのです」
――血が繋がっていないから訊けないのではない自分の進むべき道は最終的に自分で見つけるべき
助言をすることは親として当然だが“医者の子どもだから”という気持ちを味わっているレイだからこそかもしれない。
進路を決める頃、決められたレールの上だった。しかし、開発に携わることを最終的に自分で決めた。
レイが実際自分で答えを出し、“親と喧嘩してでも”と話をした時“自分が決めたのならそれでいい”と優しく微笑まれた。
それを自分は裏切った事が、今では悔やまれる部分ではあるがレイは親からその心は受け継いでおり持ち合わせていた。
「確かに……」
ベリルはコーヒーを一口含む。
そして本当に“監視”というものがなくてもやっていける二人だと心で判断していた。
「え……いえ、父親としてまだまだなのでしょうかね? アザムの思考が最近ちょっと分りかねていて……」
自信なさげに答えるレイの姿がそこにはあった。
ベリルは六年前、“お医者さん”になりたいとアザムから聞いていたため、不思議がり眉をひそめた。
レイは医者でありアザムは医者の子どもとなったのだから、そこへ進んでもおかしくは無い。
「医学書などを読んだりしてますし、数学、化学関係で分らない事は、尋ねられるのですが……何かを悩んでいるような感じで」
「直接訊いてみたら良いのでは?」
「……いえ、これは自分から話すまで、訊べきでは無い気がするのです」
――血が繋がっていないから訊けないのではない自分の進むべき道は最終的に自分で見つけるべき
助言をすることは親として当然だが“医者の子どもだから”という気持ちを味わっているレイだからこそかもしれない。
進路を決める頃、決められたレールの上だった。しかし、開発に携わることを最終的に自分で決めた。
レイが実際自分で答えを出し、“親と喧嘩してでも”と話をした時“自分が決めたのならそれでいい”と優しく微笑まれた。
それを自分は裏切った事が、今では悔やまれる部分ではあるがレイは親からその心は受け継いでおり持ち合わせていた。
「確かに……」
ベリルはコーヒーを一口含む。
そして本当に“監視”というものがなくてもやっていける二人だと心で判断していた。