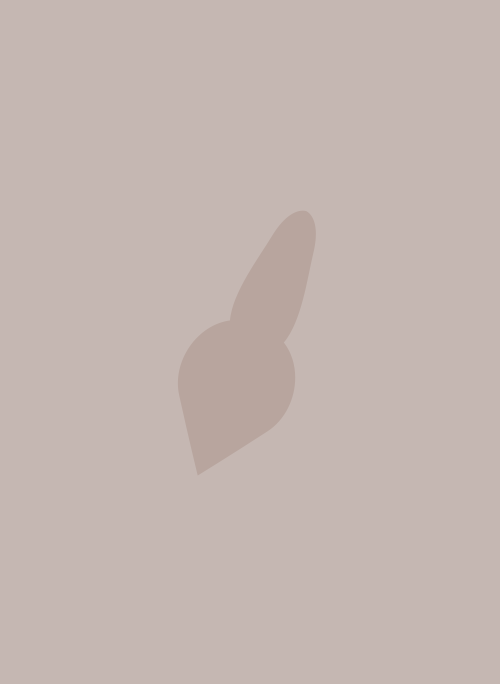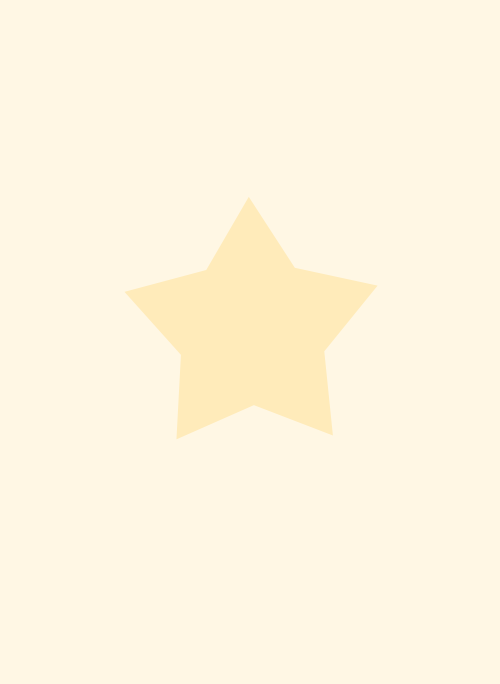「不謹慎だが、これで敵の正体が垣間見れるやもしれん。危ないと思ったらお前は退く事が第一だ」
元々中世での傭兵は雇い主や領主の名前を背負う。“敵に背中を見せるな”という昔のスタンスの名残はある。
それは退いてはならないではなく“任務を確実に遂行”という事に形は変わっているが、それくらいの心が必要な世界。
しかし、どちらにしろアザムは傭兵ではない。
決めかねている事実はあるが、一般人だという事を言葉で何処まで通じるかはともかく、理解させる事が必要だとベリル考えている。
「……わかっているよ。人をかばえば動きが鈍るのは僕が一番知っているから」
六年前の一場面を少年が思い浮かべている事がベリルにはすぐに分った。
ベリルが嘘を突き通し、大泣きしながらガソリンスタンドに引きずり出された時の事。
テロリストを混乱させるためにアザムを自分の首にしがみつかせた。
ベリルは中心人物の足を打ち抜くことには成功したが、照準は甘くなり全員の拘束にはその時点では至らなかった。
「取り合えず今度は、自分の身は少しくらい自分で守ってもらう」
厳しい言葉を吐きながら、ベリルは特注の鞘に入っている大型のサバイバルナイフをアザムに手渡した。
そう言いながらもそれは最悪な場合の護身用であり、連れて来た自分自身がアザムを絶対に護ると決めている。
そしてアザムは手渡された大型のサバイバルナイフを鞘から一度出す。そして鞘に戻すと、本当に剣のように左の腰辺りに装備し、決意の表情を浮かべた。
元々中世での傭兵は雇い主や領主の名前を背負う。“敵に背中を見せるな”という昔のスタンスの名残はある。
それは退いてはならないではなく“任務を確実に遂行”という事に形は変わっているが、それくらいの心が必要な世界。
しかし、どちらにしろアザムは傭兵ではない。
決めかねている事実はあるが、一般人だという事を言葉で何処まで通じるかはともかく、理解させる事が必要だとベリル考えている。
「……わかっているよ。人をかばえば動きが鈍るのは僕が一番知っているから」
六年前の一場面を少年が思い浮かべている事がベリルにはすぐに分った。
ベリルが嘘を突き通し、大泣きしながらガソリンスタンドに引きずり出された時の事。
テロリストを混乱させるためにアザムを自分の首にしがみつかせた。
ベリルは中心人物の足を打ち抜くことには成功したが、照準は甘くなり全員の拘束にはその時点では至らなかった。
「取り合えず今度は、自分の身は少しくらい自分で守ってもらう」
厳しい言葉を吐きながら、ベリルは特注の鞘に入っている大型のサバイバルナイフをアザムに手渡した。
そう言いながらもそれは最悪な場合の護身用であり、連れて来た自分自身がアザムを絶対に護ると決めている。
そしてアザムは手渡された大型のサバイバルナイフを鞘から一度出す。そして鞘に戻すと、本当に剣のように左の腰辺りに装備し、決意の表情を浮かべた。