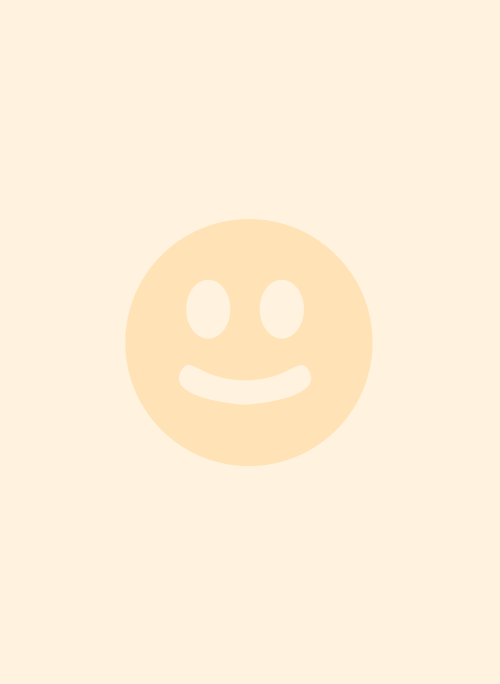すっかり暗くなってしまった。
別に寄り道していた訳じゃないのに、駅に着く頃には、太陽は完全に顔を隠してしまっている。
赤から紫、そして闇に包まれていく空。
昼間の時間がどんどん短くなっていく。
「もう今年も終わりが近いんだねぇ」
華子がマフラーに唇近くまで埋めて、そんな風に呟く。
「そうだな…」
呟いた俺の口元から、白い息がホワッと上がっていった。
別に寄り道していた訳じゃないのに、駅に着く頃には、太陽は完全に顔を隠してしまっている。
赤から紫、そして闇に包まれていく空。
昼間の時間がどんどん短くなっていく。
「もう今年も終わりが近いんだねぇ」
華子がマフラーに唇近くまで埋めて、そんな風に呟く。
「そうだな…」
呟いた俺の口元から、白い息がホワッと上がっていった。