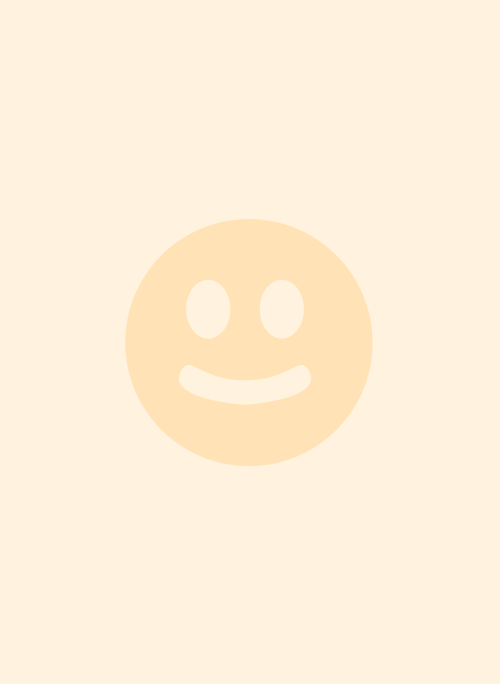「だって、紫波ってあの通りの性格じゃん?そりゃあ母性本能みたいなのが働いて構いたくなるかもしれないけど、親友ほど近くはなりたくなくない?面倒臭そうだし」
「確かにっ!」
中条は爽やかな青少年らしい笑顔を見せる。
そして、ゆっくりと、楽しそうに昔話を始めた。
「明さ、昔からあんな感じでさ。…いや、今の方がちょっとマシか」
紫波の話をする時、中条の表情は凄く優しいものへと変わる。
「クラスの皆とは仲良くしているけど、他人には絶対自分を見せないというか、いっつも1人で居ようとするのね。なんか俺そういう奴にこそ心を開いて欲しくて声を掛けたんだ」
「お人好し?」
「いいや、違うよ。ただ俺は皆に平等に接して、慕われる自分に優越感を抱きたかっただけ。だから、唯一俺にも心を見せようとしない明にムカついてたんだよね」
「あ!それ分かる!自分より更に上を行ってる感じでしょ?」
「そう!それ!」