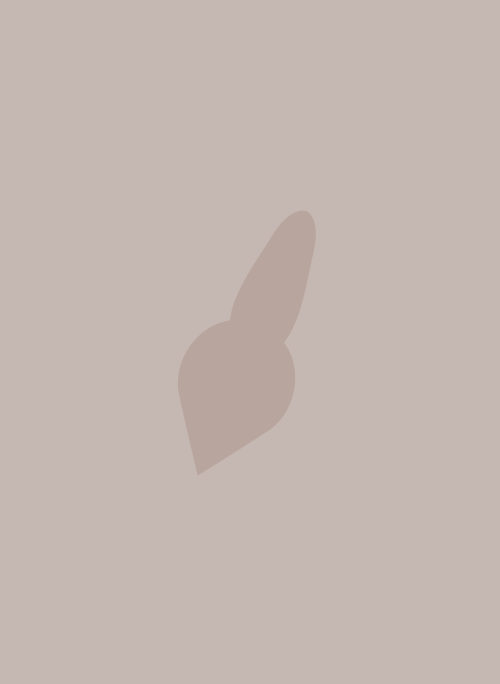俺を跳ね除けもせずに、
「この香水…ブランフォードの…」俺がつけている香水の名前を言った。
「知ってるんだ?優貴も香水使ってるの?」
抱きしめている腕は離さずに、顔だけを離して話す。
「うん。ブランフォードの…マリア。」
香水の名前を言っただけなのに、キミの涙はもっと流れた。
そして、キミは俺から顔を逸らす。
この時は、泣き顔を見られたくないから顔を逸らしたのだとばかり思っていた。
「しゃがんでるのもキツイしさ、あそこのベンチに座ろう?」
俺は、抱きしめている腕を離して、
キミを立ち上がらせるために、手を差し出す。
一瞬、ためらったかのように目を開いていたが、
キミは、俺の手を握る前に涙を拭って俺の手を握った。
「…なんで同じなの?」
ボソッとキミは呟く。
「どうした?」
「なんでもない。ベンチに早く座ろ?」
俺たちは、オブジェの向かい側にあるベンチへと足を運ぶ。