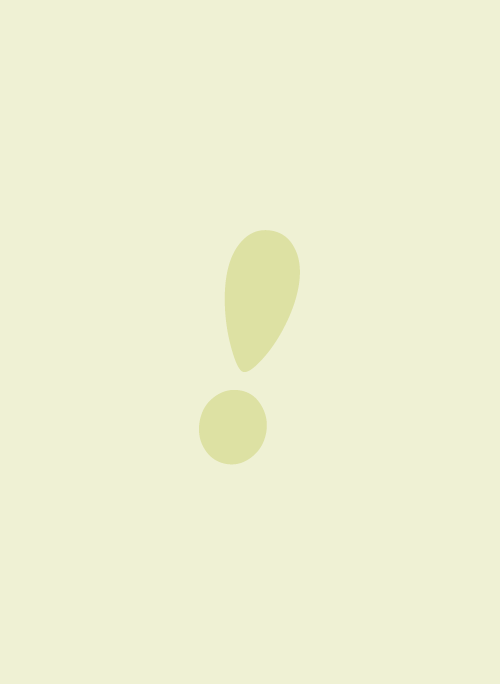別れは突然にやってくるものだと僕は知った。そしてなによりも、自分が子供で無力だということがわかった。
クリスマスを目前にひかえ、僕は舞い上がっていた。僕たちは付き合いだしてからは今までにもまして心を寄せ合うようになった。
だけどあの雪のつめたさとあおいの唇の感触、そしてあおいの言葉とともに頬をつたう涙を僕は一生、脳裏にやきつき、忘れる事はないだろう。
雪が舞い散る橋の上、僕たちは、初めて唇を重ね合わした。それは大人に一歩ちかづいたかのように感じた。だけどあおいにとっては別れの挨拶だったのかもしれない。
唇を重ね合わしながら僕は強く抱きしめるとあおいも強く抱きしめ返した。そして頬を伝うしずくを感じた瞬間、「クリスマスの約束、はたせない。ごめんなさい」とあおいは泣きながら言った。
「どうして?」と僕がきくと「お母さんと暮らす事にしたの」と言った。
その時の僕は、母と暮らすあおいの決心もこれからおこることも予想できず、ただただ無言でうつむくことしか出来なかった。
クリスマスを目前にひかえ、僕は舞い上がっていた。僕たちは付き合いだしてからは今までにもまして心を寄せ合うようになった。
だけどあの雪のつめたさとあおいの唇の感触、そしてあおいの言葉とともに頬をつたう涙を僕は一生、脳裏にやきつき、忘れる事はないだろう。
雪が舞い散る橋の上、僕たちは、初めて唇を重ね合わした。それは大人に一歩ちかづいたかのように感じた。だけどあおいにとっては別れの挨拶だったのかもしれない。
唇を重ね合わしながら僕は強く抱きしめるとあおいも強く抱きしめ返した。そして頬を伝うしずくを感じた瞬間、「クリスマスの約束、はたせない。ごめんなさい」とあおいは泣きながら言った。
「どうして?」と僕がきくと「お母さんと暮らす事にしたの」と言った。
その時の僕は、母と暮らすあおいの決心もこれからおこることも予想できず、ただただ無言でうつむくことしか出来なかった。