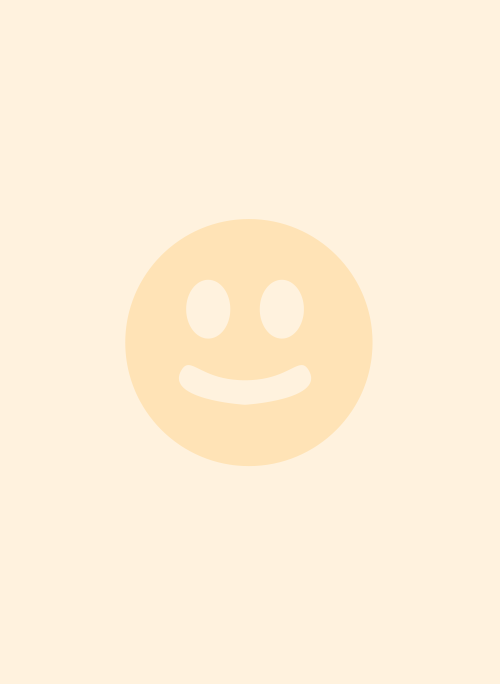「レンくんレンくん!」
日曜日の朝。僕がパジャマのまま、ベッドでごろごろしていると母さんが慌てたように僕の部屋に入ってきた。
どうせ下らないことだ。僕の休日を邪魔されて堪るか。
僕は寝たふりをしてシーツに包まっている。それでも母さんは僕なシーツを剥ぎ取った。
「すっごく美人のお友達よ!」
母さんは熱っぽく言う。まるでアイドルを見かけた時のように。
すっごく美人のお友達。僕にはそんな友達は、柚姫か愛姫しか思い付かなかった。
のっそりと僕は体を起こす。そしてそのまま玄関に向かった。
「着替えなくていいの!?」
母さんの驚いた声が後ろから聞こえた。うん、と返事をする代わりに僕は真っ直ぐ玄関に向かった。
僕は玄関のドアを開ける。果たして、待っているのは柚姫か愛姫か。
「レンっ!」
愛姫の目は兎のように真っ赤になって腫れていた。今日はあのローズヒップの香りもしない。
かと思うと、愛姫は僕の胸に縋りついてきた。声も立てずに泣いている。
「愛姫、どうしたの?」
僕はなるべく優しく聞いた。眠くて不機嫌な声になってないといいんだけれど。
愛姫は答えない。鳴咽で何も言えないのだ。何か言おうとしてもそれは鳴咽に流れる。
僕は愛姫の髪を撫でた。髪からは、微かに、だけどローズヒップの香りがした。
と、僕は気付いてしまった。母さんが父さんの腕を引っ張って、窓から僕たちの様子を伺っている。殴り倒しに行きたかったけれど、愛姫がいるからそれもできない。
愛姫が落ち着くように、と願いを込めて僕はただ愛姫を撫でる。と、やっと聞き取れた言葉は、柚姫、だった。
僕は自分でも顔が強張るのが分かる。
「柚姫がどうかしたの?」
こくり、と愛姫が頷いた。
「いなくなっちゃ――」
「家出したの?」
愛姫は首を振る。何回も何回も、その細い首が折れそうなほど左右に振る。
家出したのでないのなら、事件か。でもだったら愛姫がここに来るわけがない。
「コウキが――!」
「コウキ?」
日曜日の朝。僕がパジャマのまま、ベッドでごろごろしていると母さんが慌てたように僕の部屋に入ってきた。
どうせ下らないことだ。僕の休日を邪魔されて堪るか。
僕は寝たふりをしてシーツに包まっている。それでも母さんは僕なシーツを剥ぎ取った。
「すっごく美人のお友達よ!」
母さんは熱っぽく言う。まるでアイドルを見かけた時のように。
すっごく美人のお友達。僕にはそんな友達は、柚姫か愛姫しか思い付かなかった。
のっそりと僕は体を起こす。そしてそのまま玄関に向かった。
「着替えなくていいの!?」
母さんの驚いた声が後ろから聞こえた。うん、と返事をする代わりに僕は真っ直ぐ玄関に向かった。
僕は玄関のドアを開ける。果たして、待っているのは柚姫か愛姫か。
「レンっ!」
愛姫の目は兎のように真っ赤になって腫れていた。今日はあのローズヒップの香りもしない。
かと思うと、愛姫は僕の胸に縋りついてきた。声も立てずに泣いている。
「愛姫、どうしたの?」
僕はなるべく優しく聞いた。眠くて不機嫌な声になってないといいんだけれど。
愛姫は答えない。鳴咽で何も言えないのだ。何か言おうとしてもそれは鳴咽に流れる。
僕は愛姫の髪を撫でた。髪からは、微かに、だけどローズヒップの香りがした。
と、僕は気付いてしまった。母さんが父さんの腕を引っ張って、窓から僕たちの様子を伺っている。殴り倒しに行きたかったけれど、愛姫がいるからそれもできない。
愛姫が落ち着くように、と願いを込めて僕はただ愛姫を撫でる。と、やっと聞き取れた言葉は、柚姫、だった。
僕は自分でも顔が強張るのが分かる。
「柚姫がどうかしたの?」
こくり、と愛姫が頷いた。
「いなくなっちゃ――」
「家出したの?」
愛姫は首を振る。何回も何回も、その細い首が折れそうなほど左右に振る。
家出したのでないのなら、事件か。でもだったら愛姫がここに来るわけがない。
「コウキが――!」
「コウキ?」