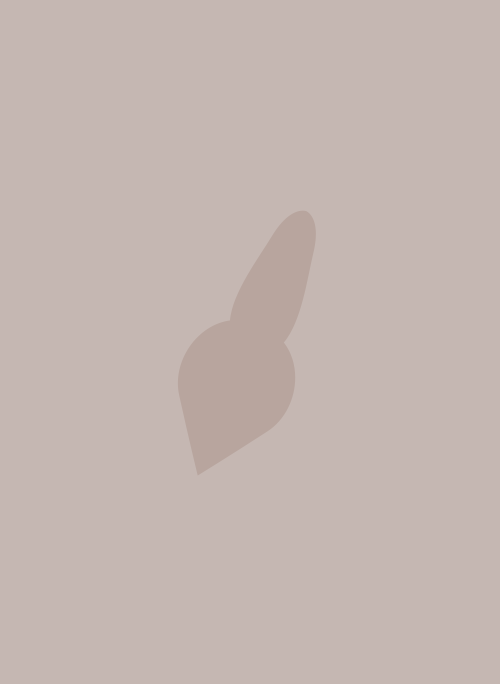「ありがとう、ごめんねこんな事頼んで。」
「水樹くんの頼みなだもん、断れないよね?!」
「ありがとう。気をつけて帰ってね!」
そんな会話の後ろで、力の入らない足でなんとか立つと、壁にもたれ歩いた。
「どこいくんだよ。」
『関係、ないでしょ…』
「…また…、そんなんで歩けんの?」
『ほっといて。 関わりたくない…』
「……。」
涙でぐしゃぐしゃな顔を見られたくなくて、ずっと俯いてた、途中しゃがみそうになるのをなんとか堪えながら。
『うっ…』
急に体が浮いた。
「ほっとけるかよ。」
『……。』
大人しく抱えられてるのは嫌だけど、歩けないんじゃ暴れても意味ないよね。
『…どうして』
「ん?」
『どうして、あの場所に居たの? 会話、聞いてたんでしょ?』
「バレてたか、いつから気づいてた?」
『「黙ってないでなんとか言え」辺りから。』
「そっか。 上手く隠れてたつもりなんだけどなぁ」
『同じ匂い、がしたから。』
「匂い?」
『うん…水樹の、香水の匂い。』
「…そっか。」
その言葉を最後に意識が途切れた。
「水樹くんの頼みなだもん、断れないよね?!」
「ありがとう。気をつけて帰ってね!」
そんな会話の後ろで、力の入らない足でなんとか立つと、壁にもたれ歩いた。
「どこいくんだよ。」
『関係、ないでしょ…』
「…また…、そんなんで歩けんの?」
『ほっといて。 関わりたくない…』
「……。」
涙でぐしゃぐしゃな顔を見られたくなくて、ずっと俯いてた、途中しゃがみそうになるのをなんとか堪えながら。
『うっ…』
急に体が浮いた。
「ほっとけるかよ。」
『……。』
大人しく抱えられてるのは嫌だけど、歩けないんじゃ暴れても意味ないよね。
『…どうして』
「ん?」
『どうして、あの場所に居たの? 会話、聞いてたんでしょ?』
「バレてたか、いつから気づいてた?」
『「黙ってないでなんとか言え」辺りから。』
「そっか。 上手く隠れてたつもりなんだけどなぁ」
『同じ匂い、がしたから。』
「匂い?」
『うん…水樹の、香水の匂い。』
「…そっか。」
その言葉を最後に意識が途切れた。