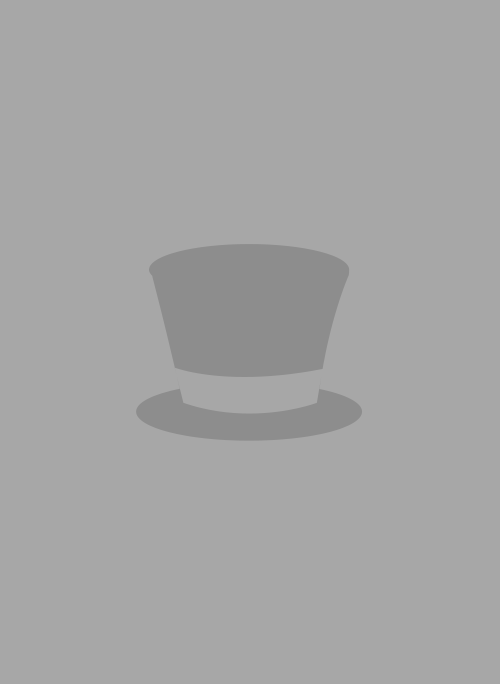あ。
五十音の一番始めの文字を型どった状態で、俺の唇は硬直する。
羽化のために地中から這い出てきたのであろうセミの幼虫が、地面に仰向けで転がっていたのだ。
どうやらうまく木に登れず落ちてしまったらしい。手足をばたつかせ、どうにか体勢を整えようと必死にもがいている。
「間抜けなセミもいるもんだなあ」
しゃがみこんで眺めながら、ははは、と軽い声をあげる。けれども笑っているのは表面だけだ。
社会人2年目の夏を迎えながら、いまだ要領よく仕事をこなす術を見つけられない俺は、助けを求めて喘ぐ小さなセミとよく似ていた。
この春に入社した新人の方が余程使えるなどと上司に怒鳴られたのは3時間前の話。係長機嫌悪いみたいだぜ、あまり気にするなよ、と同僚は励ましてくれたが気分は晴れない。
肩を落として歩く帰り道、何気なく視線を向けた道路脇の木の下に、そいつはいた。
たくさんのひとが通りすぎていく行くなか、この小さなセミの幼虫に気付いた人間は何人いただろう。どんなに懸命に助けを求めても存在を知ってすらもらえない。その哀愁がまた、悲観する自分と重なった。
盛大な溜め息をこぼし、俺はセミの幼虫を片手に立ち上がった。目の前の木に捕まらせてやる。
「お前は立派な大人になれよ」
そう声をかけると、薄暗くなり始めた街を背にのろのろと歩き始めた。
五十音の一番始めの文字を型どった状態で、俺の唇は硬直する。
羽化のために地中から這い出てきたのであろうセミの幼虫が、地面に仰向けで転がっていたのだ。
どうやらうまく木に登れず落ちてしまったらしい。手足をばたつかせ、どうにか体勢を整えようと必死にもがいている。
「間抜けなセミもいるもんだなあ」
しゃがみこんで眺めながら、ははは、と軽い声をあげる。けれども笑っているのは表面だけだ。
社会人2年目の夏を迎えながら、いまだ要領よく仕事をこなす術を見つけられない俺は、助けを求めて喘ぐ小さなセミとよく似ていた。
この春に入社した新人の方が余程使えるなどと上司に怒鳴られたのは3時間前の話。係長機嫌悪いみたいだぜ、あまり気にするなよ、と同僚は励ましてくれたが気分は晴れない。
肩を落として歩く帰り道、何気なく視線を向けた道路脇の木の下に、そいつはいた。
たくさんのひとが通りすぎていく行くなか、この小さなセミの幼虫に気付いた人間は何人いただろう。どんなに懸命に助けを求めても存在を知ってすらもらえない。その哀愁がまた、悲観する自分と重なった。
盛大な溜め息をこぼし、俺はセミの幼虫を片手に立ち上がった。目の前の木に捕まらせてやる。
「お前は立派な大人になれよ」
そう声をかけると、薄暗くなり始めた街を背にのろのろと歩き始めた。