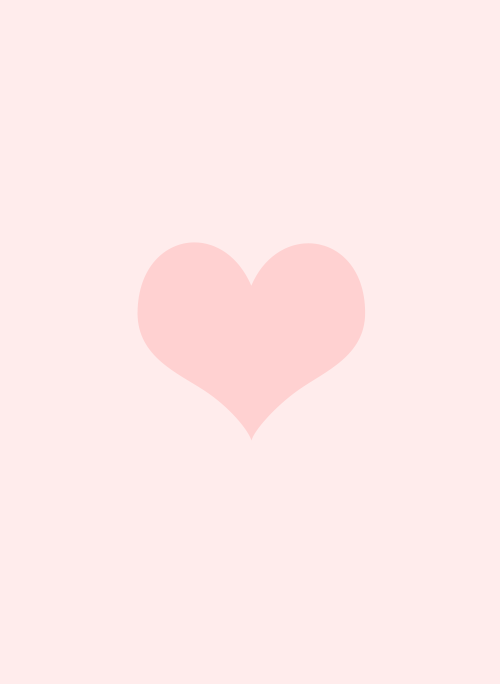「あ、星が出てる…」
黒崎君と並んで歩いていた私がふと上を向くと、夜空に沢山の星が輝いていた。
黒崎君もすぐに上を見上げて、久しぶりに見たな、と懐かしむ。
「ねぇ、黒崎君はどれが一番星かわかる?」
黒崎君は、あー…、と軽く唸ってから
「わかんねぇな。一番星って一番光ってる星のことをいうのか?だとしたらどれが一番星かなんて、人それぞれだよな」
うん。そうだ。と一人で自問自答している黒崎君。
「ふふっ」
突然笑ったことに、黒崎君は私を見つめた。
「ごめんなさい。黒崎君の考えが、私の考えと全く一緒だったから」
少し声を出して笑うと、黒崎君もそうだったのか、と言って軽く笑った。
その後も、給食に出てきた牛乳瓶の蓋が取りにくかったことや月の中に、兎がいると信じていたことなど、私たちはくだらない話をしては盛り上がった。
家にもあっという間に到着し、私は黒崎君の方へ振り返った。
「送ってくれてありがとう。すごく楽しかった」
「俺も、すごく楽しかった。」
これでやっと、安心して帰れるよ、と黒崎君は腕を上げて、背伸びした。
「それじゃ、おやすみ」
「おやすみなさい」
黒崎君が帰り、その背中が見えなくなるまで見送った後、私は温かい光が満ちている部屋へ足を向けた。