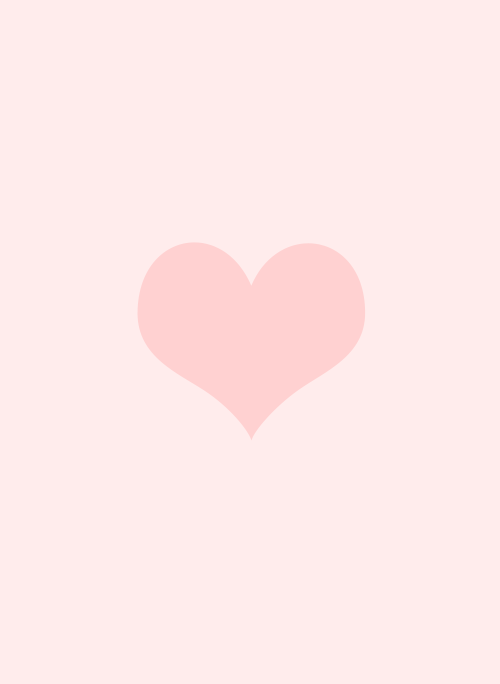そして……時は過ぎ、高校3年生。
あと1年で、身体に馴染んできたベージュのブレザーともお別れだ。
もう……"受験生"と呼ばれる学年になってしまった。
今の担任は三河《みかわ》先生。
多喜本先生よりは年下の女性教師だ。
ただ、たまに部室に鍵を返すときに、私やミツを目にすると、多喜本先生もいろいろ情報をくれる。
愛実と和貴くんは5組。
友佳と一成くんは2組。
私は、真くんと麻紀、ミツと同じ3組だ。
ミツも、いずれは自分の兄の背中を追って、検察官になるのだろう。
私は、何になりたいんだろう。
そんなとき……頭をもたげてきたのは、小学校のときの、あの学級裁判と、つい最近の模擬裁判だった。
そして、去年の面談のときに多喜本先生から言われた言葉。
弁護士。
お祖母さんも、目指していた職業。
ちょっと、興味あるかも。
進路のことを考えながらの日々はすごく早く感じた。
授業の進みもすごく早いし、試験も難しくなっていて。
体育祭もあっという間に終わった気がする。
そんな中、私は三河先生に呼び出された。
「推薦とか受けないの?
今の成績からもう少しだけ頑張ればいけるわ。
内申点も高いからね、蒲田さんは。」
先生から勧められたのは、法曹教育には実績もあり、司法試験合格率も高い大学。
私大の中では相当にレベルは高い。
「推薦枠作るの、今年が初なんだって。
相応しい生徒を2人ほど、って言われてね。
御劔くんと蒲田さんが真っ先に思い浮かんだから、声をかけてみたの。
貴女の自慢の恋人さんは、乗り気だったわよ?
大学も一緒じゃないと、むしろ恋人さんの方が気が気じゃないかもね?
っていうのはともかく、前向きに考えてみてもらえるかしら?」
三河先生は、私にパンフレットを渡した後、職員室に戻っていった。
その日の部活帰り。
三河先生に言われたことを思い出しながら、かつてミツと約束したいつもの場所で、ボーッとしていた。
進路、か。
麻紀は調理師学校、真くんとは違うところらしいけど。
友佳と一成くんは一足先に社会人。
愛実は大学に行って、社会科の教師。
和貴くんはアナウンサー志望らしい。
和貴くんなんて、レンが抜けた穴埋め、といって駆り出されるうちに、放送部の部員になっていたのだから。
皆、順調にそれぞれが、それぞれの進むべき道を決めている。
ふぅ、とため息をついたところで、頬に冷たいミルクティーが当てられる。
「ひゃ?」
変な声が出てしまった。
「ここだろうと思った。
疲れたろ、休憩。」
パキ、と音をさせて、自分は私の隣でコーヒーを飲んでいるのは、ミツだ。
「三河に推薦でも、って言われたんだろ、どうせ。
まぁ、気にするなよ。
教師っていうのはあれが仕事だ。
オレたちを少しでもいい大学に行かせる。
それが、生徒の希望通りだったら尚更だ。
教師共の株が上がるからな。
教師が何を言ってこようが、自分の希望と違ったら跳ねつければいい。」
そこで言葉を切って、放課後に校舎を出ると私の首につけられるネックレスを優しく触りながら、言うミツ。
「コレをハナにくれた幼なじみも、きっとそう言うだろうよ。
ってか、さり気なく推薦枠の話を、相手の大学に持っていったのもアイツだろうしな。
普通、実績もない学校に推薦枠なんて作らないから、おかしいとは思っていた。
……全く、余計なお世話だ。」
そういえば、彼が飛行機に乗る前。
私の首にタンザナイトと小粒のダイヤモンドが光るネックレスを着けてくれた後。
こんなことを言っていた。
「冷静な判断をもたらす石だ。
確か、ハナの誕生石のひとつでもあったはず。
……頑張れよ。
なにか困ったら遠慮なく言ってこい。
言いづらかったら、メイづてでもいいから。
最大限、コネと権力と金使って、なんとかしてやるよ。
なんてったって、大事な幼なじみだからな。」
このネックレス、いくらしたんだろう、なんて考える暇も与えないくらい、それだけ告げたあとにゲートまで歩いて行った彼。
今頃、宝月グループの当主としての勉強をしながら、ひとつ屋根の下で婚約者と過ごしているのだろうか。
「冷えると風邪引く。
そろそろ帰るか。」
立ち上がった彼の手を引き、唇を重ねた。
「ありがと、話聞いてくれて。
ちょっと楽になった。」
別に、とでも言いたげに、目を逸らすミツ。
「あんま可愛いことするな。
抱きたくなるじゃん。」
「んー、たまにはいいよ?
帰らないコースでも。
どうせ、家は隣だし。」
ぎゅ、とされて、彼の香りに包まれる。
「じゃ、そうさせて?
ってか、そうしたい。」
一度自転車で帰ってから、私の家で翌日の教科のノート等をカバンに詰めてから、彼の家に向かう。
私の母が作ったクリームシチューがお土産となったが。
あと1年で、身体に馴染んできたベージュのブレザーともお別れだ。
もう……"受験生"と呼ばれる学年になってしまった。
今の担任は三河《みかわ》先生。
多喜本先生よりは年下の女性教師だ。
ただ、たまに部室に鍵を返すときに、私やミツを目にすると、多喜本先生もいろいろ情報をくれる。
愛実と和貴くんは5組。
友佳と一成くんは2組。
私は、真くんと麻紀、ミツと同じ3組だ。
ミツも、いずれは自分の兄の背中を追って、検察官になるのだろう。
私は、何になりたいんだろう。
そんなとき……頭をもたげてきたのは、小学校のときの、あの学級裁判と、つい最近の模擬裁判だった。
そして、去年の面談のときに多喜本先生から言われた言葉。
弁護士。
お祖母さんも、目指していた職業。
ちょっと、興味あるかも。
進路のことを考えながらの日々はすごく早く感じた。
授業の進みもすごく早いし、試験も難しくなっていて。
体育祭もあっという間に終わった気がする。
そんな中、私は三河先生に呼び出された。
「推薦とか受けないの?
今の成績からもう少しだけ頑張ればいけるわ。
内申点も高いからね、蒲田さんは。」
先生から勧められたのは、法曹教育には実績もあり、司法試験合格率も高い大学。
私大の中では相当にレベルは高い。
「推薦枠作るの、今年が初なんだって。
相応しい生徒を2人ほど、って言われてね。
御劔くんと蒲田さんが真っ先に思い浮かんだから、声をかけてみたの。
貴女の自慢の恋人さんは、乗り気だったわよ?
大学も一緒じゃないと、むしろ恋人さんの方が気が気じゃないかもね?
っていうのはともかく、前向きに考えてみてもらえるかしら?」
三河先生は、私にパンフレットを渡した後、職員室に戻っていった。
その日の部活帰り。
三河先生に言われたことを思い出しながら、かつてミツと約束したいつもの場所で、ボーッとしていた。
進路、か。
麻紀は調理師学校、真くんとは違うところらしいけど。
友佳と一成くんは一足先に社会人。
愛実は大学に行って、社会科の教師。
和貴くんはアナウンサー志望らしい。
和貴くんなんて、レンが抜けた穴埋め、といって駆り出されるうちに、放送部の部員になっていたのだから。
皆、順調にそれぞれが、それぞれの進むべき道を決めている。
ふぅ、とため息をついたところで、頬に冷たいミルクティーが当てられる。
「ひゃ?」
変な声が出てしまった。
「ここだろうと思った。
疲れたろ、休憩。」
パキ、と音をさせて、自分は私の隣でコーヒーを飲んでいるのは、ミツだ。
「三河に推薦でも、って言われたんだろ、どうせ。
まぁ、気にするなよ。
教師っていうのはあれが仕事だ。
オレたちを少しでもいい大学に行かせる。
それが、生徒の希望通りだったら尚更だ。
教師共の株が上がるからな。
教師が何を言ってこようが、自分の希望と違ったら跳ねつければいい。」
そこで言葉を切って、放課後に校舎を出ると私の首につけられるネックレスを優しく触りながら、言うミツ。
「コレをハナにくれた幼なじみも、きっとそう言うだろうよ。
ってか、さり気なく推薦枠の話を、相手の大学に持っていったのもアイツだろうしな。
普通、実績もない学校に推薦枠なんて作らないから、おかしいとは思っていた。
……全く、余計なお世話だ。」
そういえば、彼が飛行機に乗る前。
私の首にタンザナイトと小粒のダイヤモンドが光るネックレスを着けてくれた後。
こんなことを言っていた。
「冷静な判断をもたらす石だ。
確か、ハナの誕生石のひとつでもあったはず。
……頑張れよ。
なにか困ったら遠慮なく言ってこい。
言いづらかったら、メイづてでもいいから。
最大限、コネと権力と金使って、なんとかしてやるよ。
なんてったって、大事な幼なじみだからな。」
このネックレス、いくらしたんだろう、なんて考える暇も与えないくらい、それだけ告げたあとにゲートまで歩いて行った彼。
今頃、宝月グループの当主としての勉強をしながら、ひとつ屋根の下で婚約者と過ごしているのだろうか。
「冷えると風邪引く。
そろそろ帰るか。」
立ち上がった彼の手を引き、唇を重ねた。
「ありがと、話聞いてくれて。
ちょっと楽になった。」
別に、とでも言いたげに、目を逸らすミツ。
「あんま可愛いことするな。
抱きたくなるじゃん。」
「んー、たまにはいいよ?
帰らないコースでも。
どうせ、家は隣だし。」
ぎゅ、とされて、彼の香りに包まれる。
「じゃ、そうさせて?
ってか、そうしたい。」
一度自転車で帰ってから、私の家で翌日の教科のノート等をカバンに詰めてから、彼の家に向かう。
私の母が作ったクリームシチューがお土産となったが。