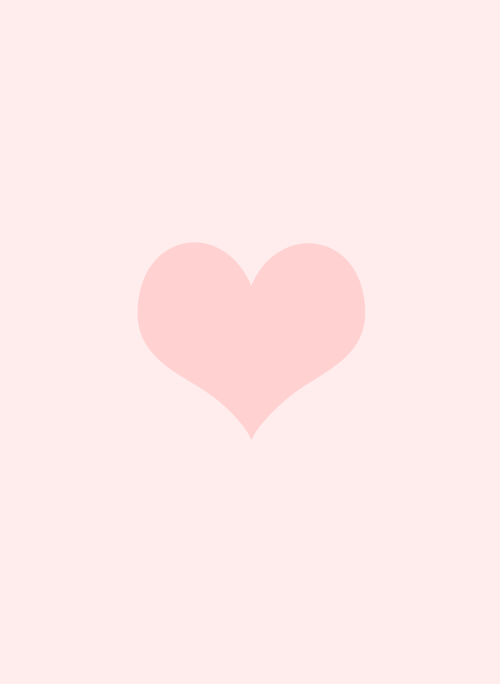友人に好きな人が居ると打ち明けることと、他人の前で服を脱いで裸になっていることは似ているような気がするくらい恥ずかしいことを、
結衣は実施中だった。
「なんか好き、好き、かっこいい……ね、普通に、ふ、カミングアウト」
ぽつり、ぽつりと声にする。
不思議なもので実際に好きだと誰かに言うと、ああ本当に好きなのだと改めて実感する。
一人で想う時より、親しい子と共有した瞬間から幸せ濃度が増したのは間違いではないはずだ。
胸の中にふんわりとした透明の粒が作られたみたいに淡い気持ちは、
両手に乗せてホッペをくっつけたくなるような甘さを伴う。
満席のフロアはトレーを持ったまま居場所のないグループが練り歩いており、
チープな雰囲気が時給八百円程度の学生には違和感なく馴染むし、むしろ映える。
「てかあれよ、好きーどしよ、好き!」
スキと言う二文字を奏でることが面白くて、嬉しくて、楽しくて、結衣は馬鹿並に好きだと連呼しまくった。
誰もそこまでリクエストしていないというのに、しつこく歌った。
そんな彼女の可愛さは人並みで、特別目立つほどの容姿ではないと思っていたのが愛美と里緒菜だが、
今自分たちの前に居るのは間違いなく可愛い女子で、
恋の魔法があるなら、彼女にもうかかっているのだと知る。
二人にとって、女子高生友情マジックから結衣は自分の子供のよう存在であり、
そうなれば最後まで見届けたくなる親心。
「熱狂的なファンじゃん、好きなんだ?」
里緒菜は故意に尋ねた。
サイン会があれば並ぶのかと冗談を交え、こんな時にも笑いを挟むのが仲良し三人組の特徴であり、結衣が好きな関係である。
そう、真剣な話ばかりより、楽しく飛躍させてトークを展開させる方が雑で愉快だと思うのだ。
ポテトフライを摘んでてらりと光る指先をこちらに向けられた。
「好き。変だよね、リアルに名前しか知らないし。残念なことに話したことないし。
それで好きとか、はは、なかなか私キモ、あはは」
入学式から今日までを振り返るのだが、恋に落ちた決定的な事実は曖昧だ。
それなのに、大好きで大好きで――片思いは異常にしか思えなかった。