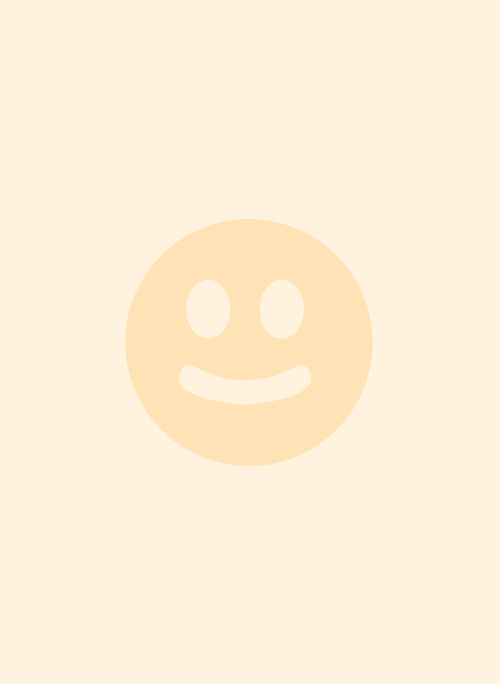私は要はやり易かったのだ。早希と比べてこの日高吏花は何も考えていないだろうし私に大した興味もないのだ。実際のところあの通りだと思う。吏花は私の視線の意味を心では理解出来なくとも身体が感じ取って、反射的に謙遜をしたのだと、思う。
でもそうやって考える自分が、私は嫌いで、世界が歪んで見えている自分が、嫌いだった。きょとんとする吏花に私は舌打ちをして目を逸らす。面倒臭い。
「でも私奈也ちゃん素敵だと思うけどな、ほんとだよ?そんな、可哀想なんて…寧ろどうして?って感じ」
吏花も立ち上がる。私に向かって首を傾げて見せた。私も首を傾げた。“素敵”?何が、どう。私の何処が、どんなだ。…少なくとも貶している訳ではないと知った私は如何いった反応を寄越したら良いのか判らず苦笑した。吏花も声を出して笑う。
「奈也ちゃん、ピアノ弾ける?片手でいいよ」
はあ、まあ、と私が云うと吏花は一段とキラキラとした雰囲気に抱かれて笑う。連弾をして欲しい、と云った。要は私が右手で弾けば曲は成り立つのだ、と。
「うん…まあ…いいよ、連弾でも何でもやってやるから」
「本当に?有難う!」
手を組み合わせて喜ぶ吏花は、何と云うか、私が素敵なら、…彼女は“奇跡”だ。