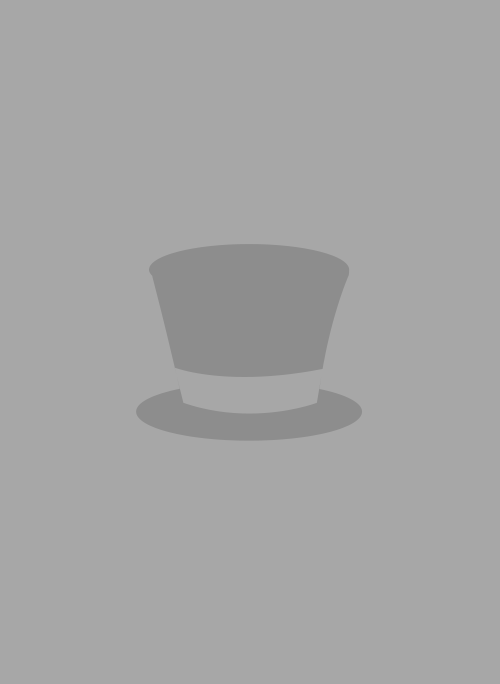「っ・・・」
気合いもむなしく、すぐに動揺してしまった。
“ピ・・・・ピ・・・・ピ‥”
ベッドに横たわるリカちゃんには、たくさんの管が通されていた。
口には酸素マスクがつけられ、体も最後に見たときよりもやせ細っている。
「り、カちゃん…」
まさかこんなに早く悪化するなんて…
命の灯りも前よりも小さく、今にも消えそうだった。
予想外すぎることが目の前で起こって、血の気はひき心臓がやけに音をたてていた。
「か・・・のん、おねえ・・ちゃん?」
っ!
「リカちゃん!」
偶然か必然か、リカちゃんが目をさました。