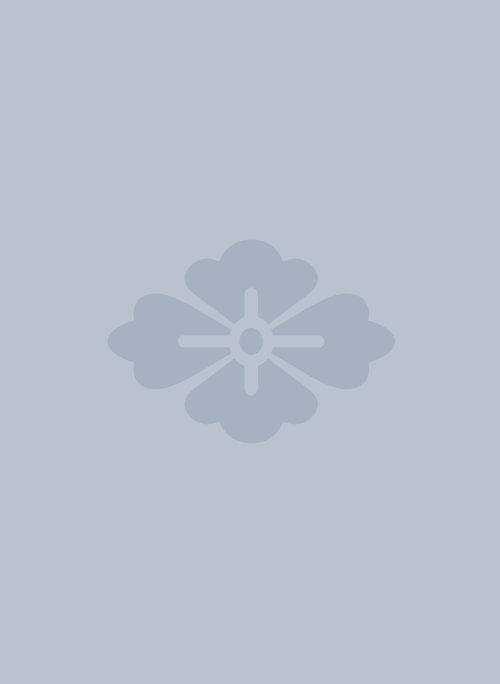龍之介がほとんど学校に来ていない、と言ったほうが正しいかもしれない。
それはまるで二人出会う以前の龍之介のように。
たまにふらりと学校に来ていたとしても、優衣を視界に入れることなくすぐに姿を消してしまう。
そんな日々がもうかれこれ一週間。
この一週間の間に優衣の中で渦巻いていた、父親思い出させる黒い感情は薄まってきて。
かわりに、一人では埋められない寂しさが優衣の全身を襲っていた。
「龍、くん…」
膝を抱え震える声で小さく呼んだ名前に大好きな声が返ってくるはずもなく。
誰もいない屋上に虚しく響くだけ。
つん、と痛む鼻の奥。
その痛みに優衣の唇がきゅっと真一文字を描いた。