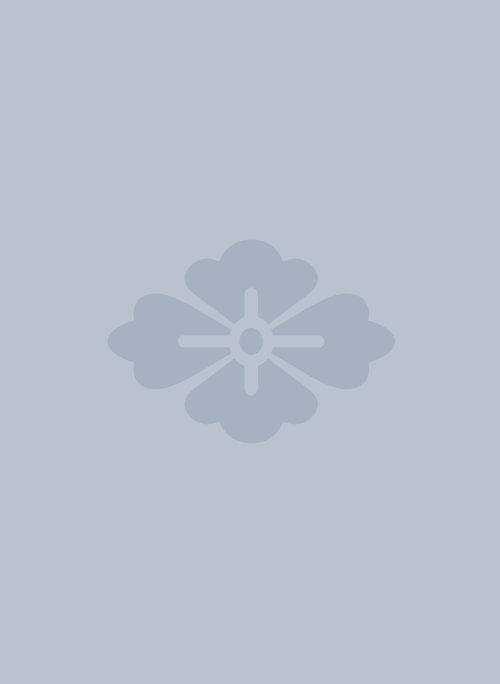(龍く、は…龍くんはそんなこと、しないんだ…もん)
頭の中ではそうわかっている。
龍之介がそんなことするような人間ではないことを。
優衣の記憶のなかにいる龍之介はいつだって優衣に優しい。
それは初めて会話らしい会話をしたあの時から変わることなくずっと。
しかし、一度芽生えてしまったもやもやとした気持ちはそう簡単には消えてくれなくて。
その原因は彼女の言葉というよりも、その"存在"と、優衣の自身に対する自信のなさだろう。
中学時代からの知り合いで龍之介のことをよく知る美人な彼女。
優衣の知らない龍之介を当前のように彼女は知っているのだ。
そんな当たり前のことが優衣の胸の奥を握り潰そうとしている。