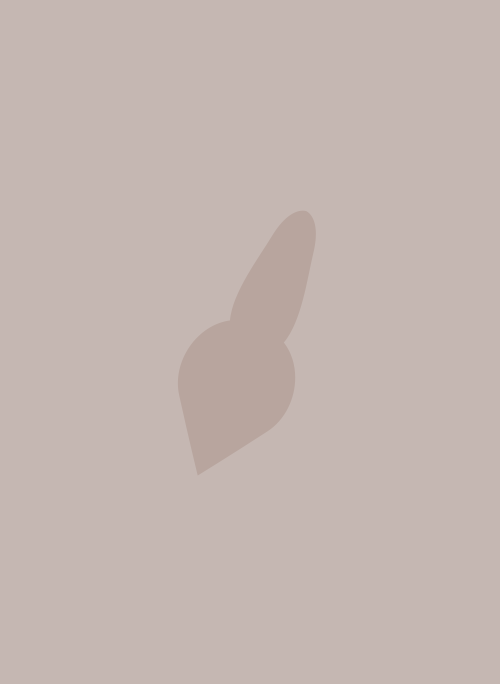「紫丞のお坊ちゃまがこちらに執事としていらっしゃったとき……このままお嬢様と一緒になるおつもりなのだと私は思って喜んでおりましたのに……」
小さいころの私たち二人をよく知る雪路さんらしい言葉に、私はまた苦笑いを浮かべた。
一緒になろうと確かに言われた。
でもできないと断ったのは他でもない私。
「彼にはもっとふさわしい人がいるし、もっと能力のある上品な人じゃなくちゃ、あの家の妻にはなれないと思うわよ」
雪路さんから小さなボストンバックを受け取りながら、私はそう答えた。
香椎くんが紫丞孝明という人である限り。
私はその横には並べない。
自分が彼にふさわしい人になればいいと……言われてしまいそうな気もする。
でも違う。
もう二度と家という束縛された環境に私自身も、今後生まれてくるかもしれない子供たちも巻き込みたくないと心底思ってのことでもあった。
「お嬢様ほど素敵な女性など私は知りません」
雪路はきっぱりとそう言い切った。
「そうね……そう育ててくれたのは雪路さんだもんね。すごく……感謝してる」
母が亡くなった後、私のことを陰になり日向になり支えてくれた一人であるメイド長に私は素直に頭を下げた。
雪路さんは驚いて、大きく首を振った後「もったいない」と大粒の涙をこぼして私の手を取った。
「なにかお困りのことがありましたらすぐに……すぐにお知らせくださいませ。お嬢様がどこにいようとこの雪路。すぐに飛んでまいりますから!!」
「うん。そうする」
にっこりとほほ笑んで、年老いた彼女の手をギュッと握りしめる。