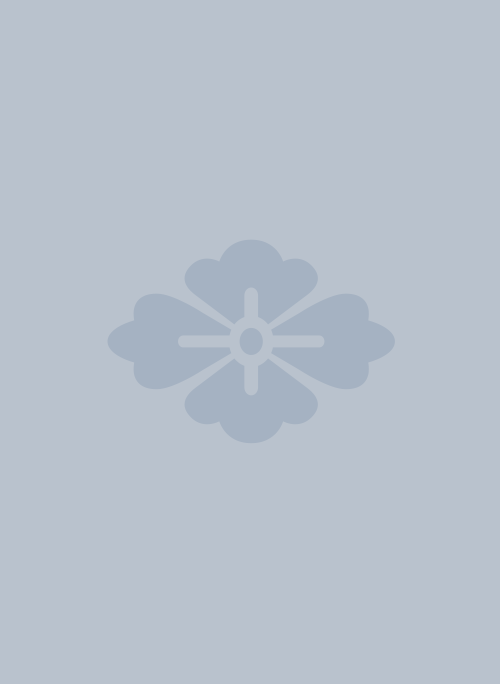「…自分で聞いといて、辛くなるとか……馬鹿じゃねぇの、俺…」
己を嘲笑うような言葉は静まり返った景色に虚しくこだまして。
まるでこの世界には自分一人しか存在しないのではないかと感じるほどに、歳三には葉の擦れる音すらも感じられていない。
何もかもが消え去ってしまったような、そんな孤独感が歳三を闇へ誘おうとしている。
何で俺は…かおに、届かねぇんだ。
何より、それだけが辛く悔しく痛かった。
あの空に浮かぶ月のように遠く、川の水のようにこの手を擦り抜け、風のように心を揺さぶる馨。
それなのに、空気のように歳三の奥底を住み着いて離れない。