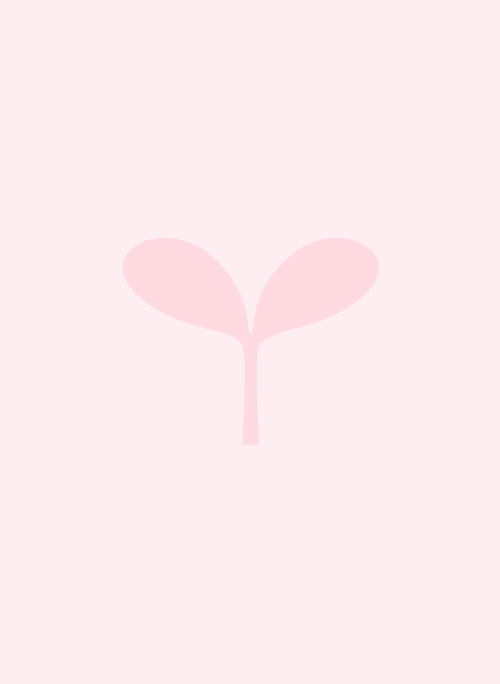覆いかぶさったままのスフェーンを見ると、スフェーンは少し心配そうな顔をしてじっとあたしを見ていたよ。
「もしさ」
落ち着いた声を取り戻したスフェーンが口を開いた。
「最初から優しくしてたら、あたしの事好きになってくれたのかな?」
『…わかんない』
その問いかけに正確には答えられない、そういう事は論理的に考えられるものじゃないんだ。
『でも』
「でも?」
『嫌いにはならなかったと思う』
あたしはあえて嫌いと言ってあげた、この状況で中途半端な事を言う事はお互いの為にならないから。
「やっぱり、嫌いなのね
あたしはあなたが昔も今も大好きなのに」
『ごめん、でもそう思うんだからしょうがないんだ』
「わかったよ、すっごく嫌かもしれないけど
後1度だけいい思い出を見させて…最後のわがままだと思って」
スフェーンはさっき噛み付いた所に点々と出て玉になっている血をやさしく舐めた。
あたしはその様子を見て、スフェーンに対する気持ちは変わらないけれど、やさしく髪を撫でてあげた。
「もしさ」
落ち着いた声を取り戻したスフェーンが口を開いた。
「最初から優しくしてたら、あたしの事好きになってくれたのかな?」
『…わかんない』
その問いかけに正確には答えられない、そういう事は論理的に考えられるものじゃないんだ。
『でも』
「でも?」
『嫌いにはならなかったと思う』
あたしはあえて嫌いと言ってあげた、この状況で中途半端な事を言う事はお互いの為にならないから。
「やっぱり、嫌いなのね
あたしはあなたが昔も今も大好きなのに」
『ごめん、でもそう思うんだからしょうがないんだ』
「わかったよ、すっごく嫌かもしれないけど
後1度だけいい思い出を見させて…最後のわがままだと思って」
スフェーンはさっき噛み付いた所に点々と出て玉になっている血をやさしく舐めた。
あたしはその様子を見て、スフェーンに対する気持ちは変わらないけれど、やさしく髪を撫でてあげた。