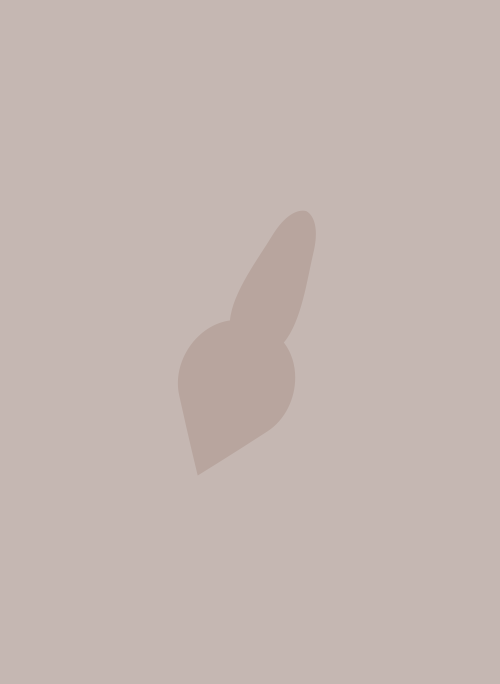「さらに真っ白になった気がする。君に洗われて嬉しがってるみたいだ。」
「そうですか?なんか嬉しいです。」
まさか神田くんが、帽子が嬉しがってる、なんてメルヘン?な事を言うと思ってなかった私は、褒められた気がして少し嬉しくなった。
「ま、この帽子くんは僕に懐いてるんですけどね。」
フン、と自信満々に言い張る神田くん。
「なんですか、その意味のない対抗は。」
「とにかく!
帽子くんは僕の方が好きって事です。」
「はいはい。
帽子くんは神田くんが大好きですよ。」
「そんな投げやりな…。」
完全に拗ねてしまって、ブツブツ言っている神田くんを横目に、私はケーキバイキングを注文した。