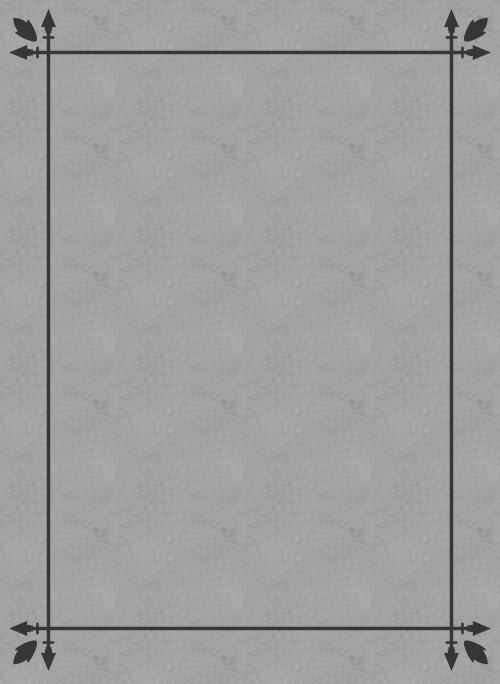本当に真面目に講義を受けて。
必死に、頑張ってたんだ。
でも、どうしてそこまでして。
何とも言えない感情が沸き上がってくる。
「時雨が此処に戻って来なくても、俺が支えてやれるような人間になって絶対に迎えに行く」
握っている手に額を当てて再び俯いた拓斗君。
そうやって、時雨さんが居なくなった後も考えて、
自分を責めて背負い込んで。
……時雨さんは酷い人だ。
自分が黙って居なくなって、
その後拓斗君が自分を責めて苦しんでしまう事まで考えなかったの?
ずっと隣に居たのに考え付かなかったの?
拓斗君が可哀想。
そう思って、でも何故かそこまでできる拓斗君が愛しくなって。
そんな自分を追い詰めるような苦しみから解放してあげたくて。
―――気付いたら体は勝手に動いて。
俯いたまま動かない拓斗君を、正面から包み込むように抱き締めた。
抱き締められても腕のなかの拓斗君は微動だにしない。
「……そんなに苦しそうな顔、しないで」
拓斗君の髪に指を絡ませる。
「無理に、頑張り過ぎないで」
お願いだから。