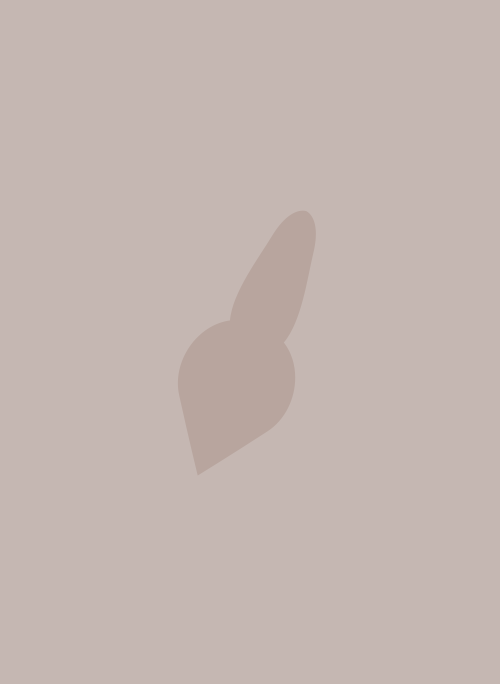*
「四条さん!」
目の前で、そのくりくりの瞳をしっかりとあたしに向けながら、僚右君がにっこりと微笑む。
瞳にあたしが映ってる。
「ん、行こう?」
あたしもにっこりと微笑み返して、僚右君に並んだ。
やっぱり僚右君は人気助教授なのか、大学の前で親しげに話すあたしたちは、注目の的だった。
だけど気にする様子も全くなく、僚右君は笑う。
本当に、渚とは大違いだ。
優しい瞳も、笑顔も、全部渚にはなかった物。
世間一般からみたらよっぽどこっちの方がいいって言われるのに、なんでかあたしはあんなのを5年も追いかけていた。
冷たくて、こっちを見もしなくて、銀色の瞳に銀色の髪。
声まで冷たいまま、“仁那”って呼ぶんだ。
「どこに行きたい?」
「え、あ…どこでもいいよ」
視界に入り込んでくる僚右君に、ハッとして笑顔を作った。