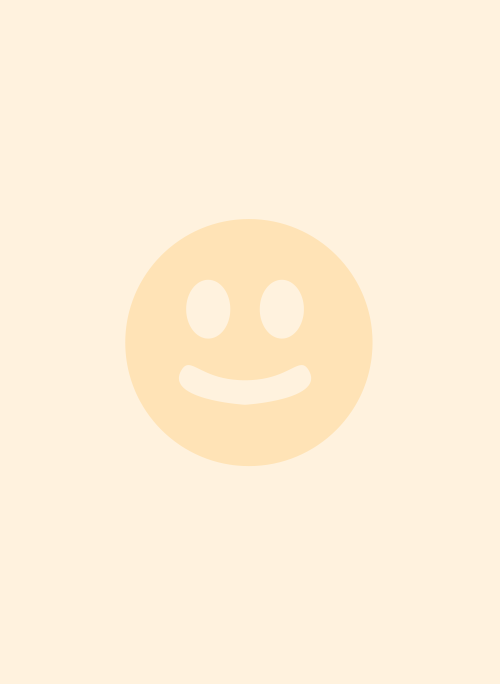「油断したわぁぁ!!!」
私は扉を叩いた。
いくらたたいても、ビクともせず、木のギシギシという音が鳴るだけ。
外から鍵が掛けられてるー…!
あかないよぉ。
「あ~け~て~!」
「無理です。朝ごはんはそこにおいてあります。どうぞ、食べてください。失礼な言い方ですが…貴方が考えてることはたかがしれてます。どうぞあきらめるという気持ちを知ってください」
小さな机にある高価なお皿。
スープとティーカップの中に冷めたミルクティー。
堅くなったクロワッサン。
水気のないオレンジ一つ。
「…私の昨日のこと、覚えてないの?私は、あなたとクビにできる!」
「…失礼ですが、私を雇っているのは『国王、あなたのお父様』です。国王さましか、私をクビにできません。…食べ終わりましたら、メイドにお渡し下さい」
…胸に、何か刺さったようだった。自然と、涙があふれ出てくる。
メイド…シルト!
じゃあ、扉も開くわ!そのとき…
「あ。もちろん、外には警備員が30人ほどいますので。あいたときに逃げたって意味ありませんから。では、私は仕事がありますので」
マロンは靴を鳴らしてパソコンの音をなびかせながら階段をリズム良く降りていった。
「っふ…」
涙で頬がぬれてゆく。乾いた木の床に、私の涙は落ちてゆく。
クロワッサンを入るだけ口に詰め込み、スープで流し込む。
「っく…悔し…」
ミルクティーはすっかり冷たくなっている。いつからおかれていたのか、物語っていた。
…まって?
そういえば…
窓!!
そこから逃げ出せるじゃない!!
「やだ、ナイスな考え!」
ぱっと下をのぞくため窓を開ける。