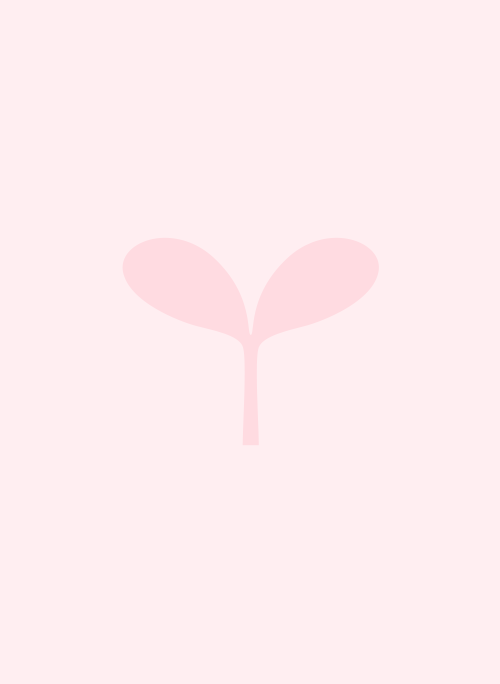反対派と違い、賛成派は皇王夫婦に疑われる要素をもたない。リンド公はこれまで以上に皇族という身分に一番近くなった。賛成派の他の人物も認めるほどの家柄もある。
『陛下はセリナ様を後嗣になさろうと考えていらっしゃる。いくら反対派が多いとはいえ、決定権はすべて陛下がおもち……となるとセリナ様は女皇王となられるだろう』
まだ皇女が幼い時からすでにそのように考え、セリナ本人に接するようになった。
途中、皇子リュカが生まれてもその考えは変わらなかった。というのも、皇王の考えを知っていたからこそ安心できていた。
いくら反対派が募ろうとも、烏合の衆。こちらは絶対的な皇王の考えのもと動いているのだから。
後嗣は変わらず皇女のまま。そしてその皇位を継ぐ時、賛成派であった自分が家臣の中では一番近い存在になる。
これまでの仲間……煩かった古参の貴族は一掃され、自分が最も力を得た貴族になる。
過激化する派閥争いにいつしか、純粋な忠誠心よりも自分の欲の方が勝ってしまっていた。
気付いた時にはもう遅い。妄執に囚われ、自分に有利なことしか考えないようになっていた。
欲が増す。次に考えたことは、皇女が女であることを利用した策――息子をも利用し内戚になろうということ。
リンド公には皇女と年齢的にも釣り合う息子が二人いた。その二人ともを利用しようと。
まずは長男。故郷ミゼット州で住まう息子に「将来、爵位を継いだら皇女に婿入りをしろ」ということを言ってきかせた。
次男は都に行かせ、皇女の護衛騎士にさせようとした。もし長男が気に入らなかったら、より年の近い次男もいる。
それに次男はいい年になっても遊び呆けている。騎士団に入れ、その曲がり切った根性を叩き治せればなおよし、とまで考えていた。
『陛下はセリナ様を後嗣になさろうと考えていらっしゃる。いくら反対派が多いとはいえ、決定権はすべて陛下がおもち……となるとセリナ様は女皇王となられるだろう』
まだ皇女が幼い時からすでにそのように考え、セリナ本人に接するようになった。
途中、皇子リュカが生まれてもその考えは変わらなかった。というのも、皇王の考えを知っていたからこそ安心できていた。
いくら反対派が募ろうとも、烏合の衆。こちらは絶対的な皇王の考えのもと動いているのだから。
後嗣は変わらず皇女のまま。そしてその皇位を継ぐ時、賛成派であった自分が家臣の中では一番近い存在になる。
これまでの仲間……煩かった古参の貴族は一掃され、自分が最も力を得た貴族になる。
過激化する派閥争いにいつしか、純粋な忠誠心よりも自分の欲の方が勝ってしまっていた。
気付いた時にはもう遅い。妄執に囚われ、自分に有利なことしか考えないようになっていた。
欲が増す。次に考えたことは、皇女が女であることを利用した策――息子をも利用し内戚になろうということ。
リンド公には皇女と年齢的にも釣り合う息子が二人いた。その二人ともを利用しようと。
まずは長男。故郷ミゼット州で住まう息子に「将来、爵位を継いだら皇女に婿入りをしろ」ということを言ってきかせた。
次男は都に行かせ、皇女の護衛騎士にさせようとした。もし長男が気に入らなかったら、より年の近い次男もいる。
それに次男はいい年になっても遊び呆けている。騎士団に入れ、その曲がり切った根性を叩き治せればなおよし、とまで考えていた。