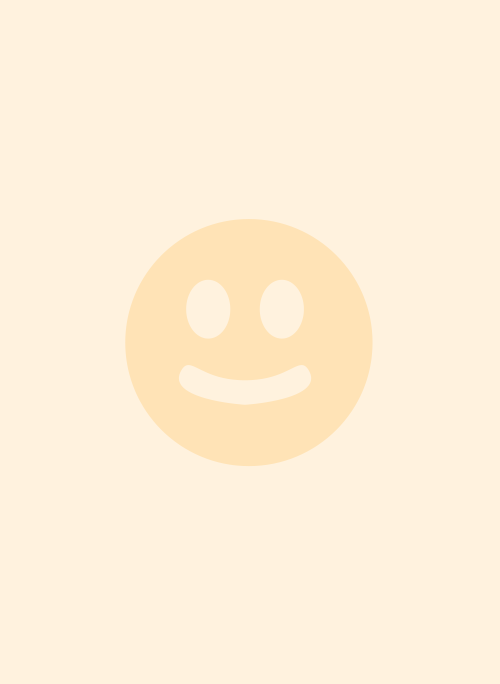やがて。
俺は手綱を引いて愛馬を停止させる。
…湖からも、川からも相当距離をとった。
「さぁハルパス、どうする?」
今度は俺が語りかける番だった。
「貴様お得意の『水鉄砲』ももう使えまい。大人しく姿を現したらどうだ?」
水辺から距離をとった理由はそれだった。
ハルパスは湖や川の水を体内に取り込み、それを勢いよく噴出する事で圧縮した水の弾丸を作り出し、それで俺を狙撃していたのだ。
説明だけ聞けば耳を疑うような話。
だが。
「出てきたか」
俺の目前に姿を晒したハルパスのこの醜い姿を見れば、奴の水鉄砲の威力も納得できる。
俺の前に現れたのは、深緑色の鱗に全身を覆われた醜悪な人型の生物だった。
刺々しい背鰭。
両手両足の水掻き。
一歩地面を踏み締める度に、湿った足音が聞こえる。
まるで魚類と人間の合成生物(キメラ)の如き生命体。
我が屋敷の猟場番、カルロス・ハルパスの正体は、南米アマゾン川を棲みかとする半魚人だったのだ。
俺は手綱を引いて愛馬を停止させる。
…湖からも、川からも相当距離をとった。
「さぁハルパス、どうする?」
今度は俺が語りかける番だった。
「貴様お得意の『水鉄砲』ももう使えまい。大人しく姿を現したらどうだ?」
水辺から距離をとった理由はそれだった。
ハルパスは湖や川の水を体内に取り込み、それを勢いよく噴出する事で圧縮した水の弾丸を作り出し、それで俺を狙撃していたのだ。
説明だけ聞けば耳を疑うような話。
だが。
「出てきたか」
俺の目前に姿を晒したハルパスのこの醜い姿を見れば、奴の水鉄砲の威力も納得できる。
俺の前に現れたのは、深緑色の鱗に全身を覆われた醜悪な人型の生物だった。
刺々しい背鰭。
両手両足の水掻き。
一歩地面を踏み締める度に、湿った足音が聞こえる。
まるで魚類と人間の合成生物(キメラ)の如き生命体。
我が屋敷の猟場番、カルロス・ハルパスの正体は、南米アマゾン川を棲みかとする半魚人だったのだ。