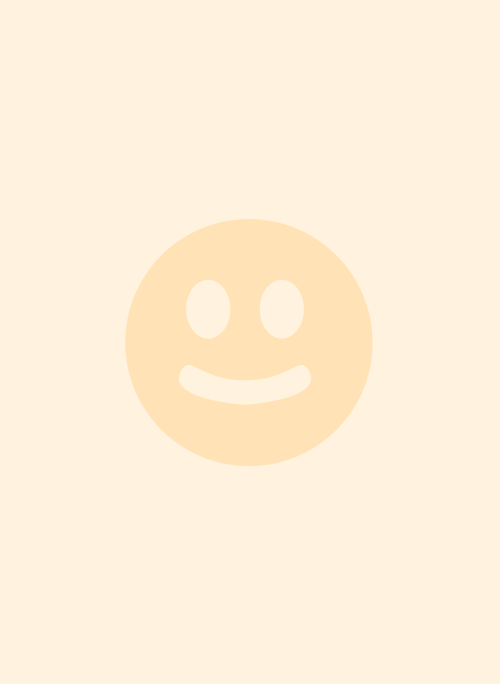やがて馬は、樹海の中の少しひらけた場所に出る。
そこは、ちょっとした湖だった。
波さえ立たぬ穏やかな水面。
まるで鏡面の如き静寂の湖面には、天に輝く月が映り込む。
足を踏み入れた人間を彷徨わせ、迷宮の如く脱出不可能にさせる魔の樹海の中に存在するとは思えぬほど、その湖は幻想的な光景を湛えていた。
「綺麗…」
その美しさに魅せられたのか、俺と共にいる事も忘れてリルチェッタが呟く。
「殺し殺される日常に生きる俺とて、この湖の神秘的な美しさに惹かれて時折愛馬を走らせる。周囲を取り巻く人間どもの腹黒さと違って、自然の美しさには裏がないからな」
俺はそう呟き、またリルチェッタの顔を見た。
「二心ある者との化かし合いに、俺とて疲れる事もあるのだ」
「…それはあてつけですか。来栖様」
主人への言葉遣いは保っていても、そこに俺への忠誠はない。
あくまで俺は、この女の仇に過ぎないという訳だ。
そこは、ちょっとした湖だった。
波さえ立たぬ穏やかな水面。
まるで鏡面の如き静寂の湖面には、天に輝く月が映り込む。
足を踏み入れた人間を彷徨わせ、迷宮の如く脱出不可能にさせる魔の樹海の中に存在するとは思えぬほど、その湖は幻想的な光景を湛えていた。
「綺麗…」
その美しさに魅せられたのか、俺と共にいる事も忘れてリルチェッタが呟く。
「殺し殺される日常に生きる俺とて、この湖の神秘的な美しさに惹かれて時折愛馬を走らせる。周囲を取り巻く人間どもの腹黒さと違って、自然の美しさには裏がないからな」
俺はそう呟き、またリルチェッタの顔を見た。
「二心ある者との化かし合いに、俺とて疲れる事もあるのだ」
「…それはあてつけですか。来栖様」
主人への言葉遣いは保っていても、そこに俺への忠誠はない。
あくまで俺は、この女の仇に過ぎないという訳だ。