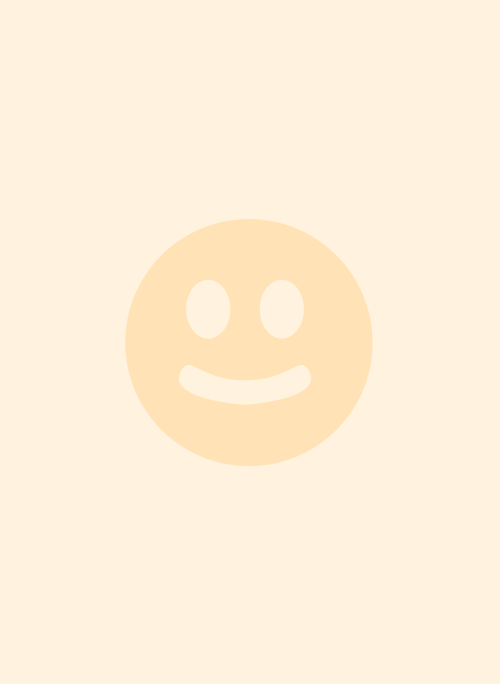足をばたつかせ、暴れるリルチェッタ。
「そんなにスカートの奥を見せ付けたいのか?暴れては下着が丸見えだ」
「えっ…!」
俺の言葉に彼女は頬を赤らめ、急に大人しくなる。
その隙に俺は鐙(あぶみ)に足をかけ、愛馬の背中にまたがった。
そして肩に担いだリルチェッタを、俺の前に座らせる。
ちょうどリルチェッタを後ろから抱きしめるように騎乗した形だ。
「っ…!」
振り返り、キッと俺を睨むリルチェッタ。
両親の仇である男と、こんな密着した状態での騎乗。
恐らくは怖気が走る、嫌悪を感じる程度の感情では済まされない筈だ。
だが彼女は、その感情をグッと堪える。
復讐を遂げる好機。
完全に二人きりになれるまで、ここは耐えなければならない。
「さて、ならば」
俺は鐙にかけたままの両足で、愛馬の腹を軽く蹴る。
「出発するか」
「そんなにスカートの奥を見せ付けたいのか?暴れては下着が丸見えだ」
「えっ…!」
俺の言葉に彼女は頬を赤らめ、急に大人しくなる。
その隙に俺は鐙(あぶみ)に足をかけ、愛馬の背中にまたがった。
そして肩に担いだリルチェッタを、俺の前に座らせる。
ちょうどリルチェッタを後ろから抱きしめるように騎乗した形だ。
「っ…!」
振り返り、キッと俺を睨むリルチェッタ。
両親の仇である男と、こんな密着した状態での騎乗。
恐らくは怖気が走る、嫌悪を感じる程度の感情では済まされない筈だ。
だが彼女は、その感情をグッと堪える。
復讐を遂げる好機。
完全に二人きりになれるまで、ここは耐えなければならない。
「さて、ならば」
俺は鐙にかけたままの両足で、愛馬の腹を軽く蹴る。
「出発するか」