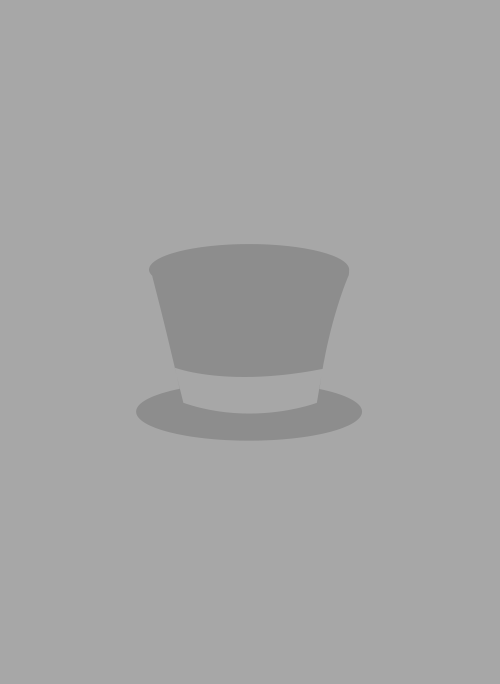「お客さん、起きてよ!」
歯無の耳元に大きな声で、怒鳴るので、目を開けた。
夢だった。
なら最高だ。
状況が頭の中を巡り、また眠りたいと、思うがタクシーの運転手は許さないと、言うきつい視線が歯無を完全に現実に戻すのだ。
タクシーは歯無を降ろすと、この場から早く離れようと、猛スピードで去って行った。
江利牧は料金を支払い、歯無を見捨てたのだ。
「あっ!」
歯無が声を上げた。もう、外は真っ暗で、半袖、短パンの上に裸足なので、すぐに寒さを感じたからだ。
歯無の耳元に大きな声で、怒鳴るので、目を開けた。
夢だった。
なら最高だ。
状況が頭の中を巡り、また眠りたいと、思うがタクシーの運転手は許さないと、言うきつい視線が歯無を完全に現実に戻すのだ。
タクシーは歯無を降ろすと、この場から早く離れようと、猛スピードで去って行った。
江利牧は料金を支払い、歯無を見捨てたのだ。
「あっ!」
歯無が声を上げた。もう、外は真っ暗で、半袖、短パンの上に裸足なので、すぐに寒さを感じたからだ。