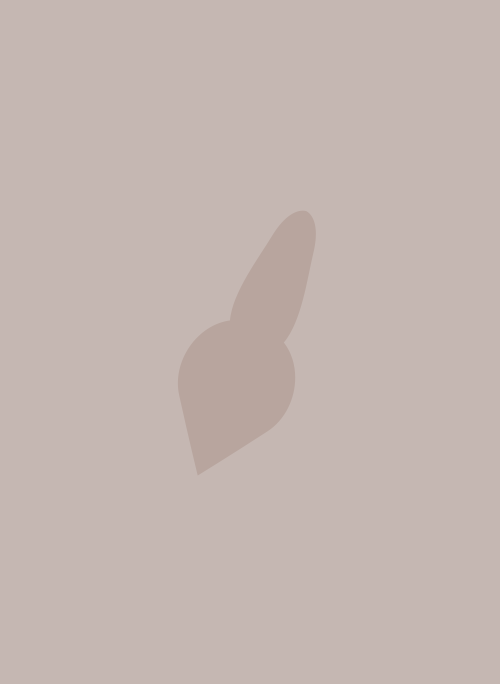そこへ、一本の電話が部屋に鳴り響いた。
テレビの横にある事務机の上の電話のランプがチカチカ光っている。
反射的に、電話を取った、私。
「はい。こちら…
「おい!何やってんだよ!」
この声は……
「菅原…さん?」
「っとに!なに普通に働いてんだよ、お前は!」
「だって…私、別に出るとは…
「馬鹿やろうっ!!」
思いの外大きい声に、
受話器を握っていない店長までもが目を見張る。
「ば、馬鹿やろうて…」
「お前が、そんなんだろうと思ってさ、俺がエントリーしといてやったよ。」
…なん…ですって?
「だからさ、コーヒーショップで働いてないで、今日はこっちに来い!
いいか?!絶対だからな!」
「ちょっ…ちょっと!」
――ツーツーツー…
耳に虚しく響く、
もう相手とは話せないという、
サイレン。
「栗田…どうするんだ?」
「…行きません。」
「お前、それでもいいのか?」
テレビには、1人目のオーディションが始まっている映像が映し出されていた。
私より、幼い少女。
どうやらキーボードでの弾き語りのようだ。
「私は…もう、アーティストになろうなんて思ってません。
今のままが、いいんです。」
「そうじゃないよ、栗田。」
「…え?」