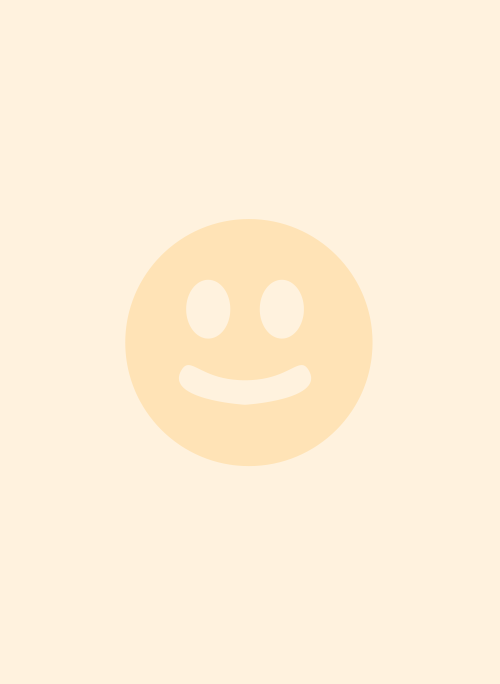エレベーターを降りて角を曲がった時、部屋に入っていく影が見える。
いいこと思い付いちゃった。
足を止めたのは僕の部屋……の一つ手前。
肘でなんとかチャイムを鳴らすと
「はい……。」
と、恐る恐る顔を出したのは泣き腫らしたような赤い目だった。
"佐伯杏奈"
「杏奈ちゃん、甘いもの好き?」
「へ?」
"馬鹿男と付き合う面倒臭い女"
「ケーキとかチョコとかクッキーとか。」
「好きですけど………、え?」
腕いっぱいにラッピングされた袋や箱を抱えた僕を不思議そうに眺める。
「これ全部あげる。」
「全部って…、え?どういうことですか?」
"関わらないのが身のため"
_