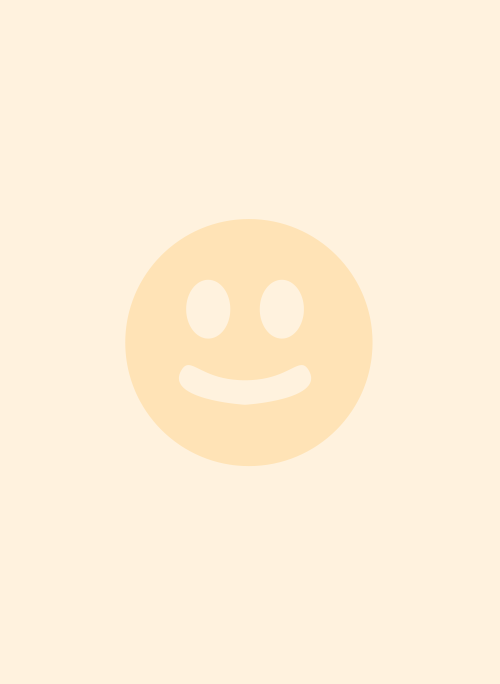体育館の両脇に設置されているスピーカーによって拡大された声が僕をステージ上へ呼ぶ。
生徒会長。
前生徒会メンバーからの指名で決まったそれが春からの僕のポジション。
「2年の小森一悟です。この度は……「「「「「キャーーー」」」」」
挨拶を始めて間もなくマイクを通しているはずの自分の声さえ聞こえなくなる。
写メを撮る音まで聞こえる中で適当に挨拶を済ますとステージを下りて元居た場所へと戻る途中
「お疲れ。今日も凄いな、小森の人気は。」
3月だというのに黒く焼けた顔からやけに白い歯を覗かせて笑う体育教師が馴れ馴れしく肩に手を置いてきても
分かってるなら止めろよ。
なんて本音は置いといて
「いえ、そういうのじゃないですから。」
と、愛想よく笑ってみせる。
「俺も昔はお前くらいイケメンだったはずなんだけどなぁ…。」
「は、はぁ………。」
どう考えてもイケメンには程遠い顔の相手を目の前に、フォローしきれない。
「はっはっは、嘘に決まってるだろーが。」
「嘘、ですか…。あはは………。」
だろうね。
点数稼ぎの笑いを残して足早にその場から去った。
_