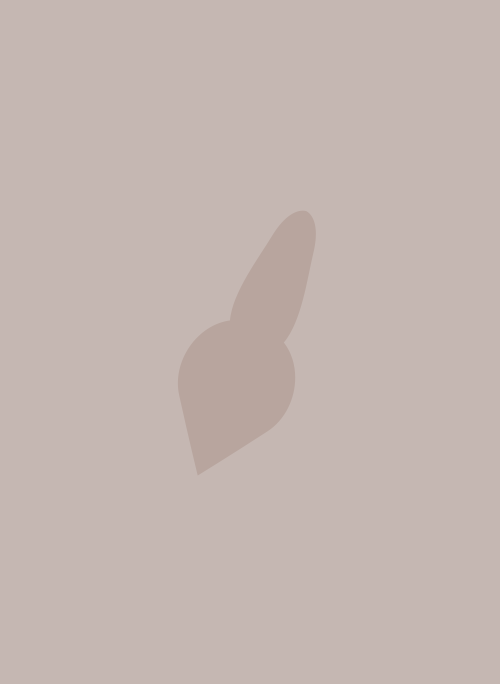その後すぐにダルコに教えてもらった連絡先に電話をする。
<……ん? 誰だ?>
対応は訝しげだが、知らない番号からかの電話に出てくれているのだから良心的だ。“誰”と言われている言葉もあまり聞こえてはいないため、自分の用件だけを話す。
『き、君は……ベリルという傭兵か?』
<そうだが? 私に何か?>
<時間が無い! アメリカ、オマハ市……今の私の地点で一番近い場所の町に来て欲しい……今から私も向う>
会話の途切れている一、二秒が分単位に感じるティーロにベリルは答えを出した。
<……一応、場所は読み取れた。分かった、どうにかする>
そう言って電話を相手側“ベリル”は切った。
ティーロは必死でここから一番近い町まで向かう事に専念した。
“どうにかする”その言葉は、ティーロにとっては“来る”の確信だった。声だけだったが、そう思える不思議な安心感にも似た雰囲気。
<……ん? 誰だ?>
対応は訝しげだが、知らない番号からかの電話に出てくれているのだから良心的だ。“誰”と言われている言葉もあまり聞こえてはいないため、自分の用件だけを話す。
『き、君は……ベリルという傭兵か?』
<そうだが? 私に何か?>
<時間が無い! アメリカ、オマハ市……今の私の地点で一番近い場所の町に来て欲しい……今から私も向う>
会話の途切れている一、二秒が分単位に感じるティーロにベリルは答えを出した。
<……一応、場所は読み取れた。分かった、どうにかする>
そう言って電話を相手側“ベリル”は切った。
ティーロは必死でここから一番近い町まで向かう事に専念した。
“どうにかする”その言葉は、ティーロにとっては“来る”の確信だった。声だけだったが、そう思える不思議な安心感にも似た雰囲気。