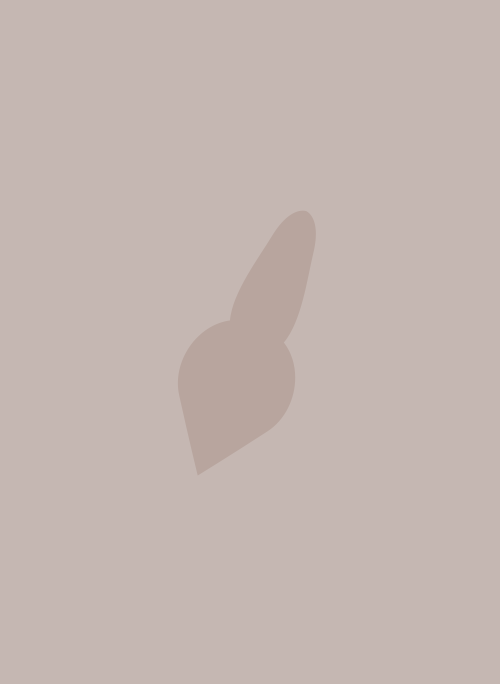アザムは既に一時間ほど待たされている。その間に冷蔵庫にあったオレンジジュースで空腹を満たしていたのだ。
そして首にかけているペンダントを開き眺めていた。そこには両親と自分と母が抱える布に包まれた赤子が写っていた。
(この写真が本当のボクの家族……)
アザムはこの部屋で一人、写真の中の『家族』失った日からの日々を思い出していた。
すると“カチッ”と鍵の開く音がして、済まなそうな顔を扉の隙間から覗かせるレイの姿があった。
「レイさん遅いじゃないか! 待ちくたびれたしジュースも全部飲んじゃった! けど、おじさんは社長さんだからボクより優先だよね」
「本当に申し訳ない。後料理を持ってきたので、扉を開いてくれませんか?」
そう言われペンダントをそのままテーブルに置くと、アザムが扉を開ける。
ワンプレートにハンバーグとパン、スープをトレイに乗せてここに戻ってきたのだ。トレイごと一度テーブルに置き向いになるように料理をセットする。
その時レイが開いたままのペンダントに気が付き、思わず手にとる。
「これはアザム君の本当の……」
レイはその本当の家族との写真の中の笑顔のアザムを見て表情が一瞬固まる。
今絶対に“抱いてはいけない”感情が……上層部の人間として、生きるためにも捨てるべき感情。
アザムは“返して欲しい”とレイに手を伸ばした。
それに気付きレイは我に返ったような感覚になる。レイに首にかけてもらうと胸元に入れる。
「けどおじさんをいつか、“おとうさん”って言える様になるまでだから。ねえ、もうお腹ぺこぺこなんだ! 食べていい?」
「ああ、遅くなって本当にごめんね。じゃあ冷めないうちに食べましょうか?」
アザムの故郷での暮らしや、学校の様な場所で英語はこれからは必要だと言われ必死に覚えた事とか。
アザムにとって話した内容は、無難で些細な事ばかりだったかも知れない。‘これから’の生活への子どもなりの気遣い。
それであっても話せば話すほど、聞けば聞くほど自分が分らなくなるレイ。それを隠し通しながらその話に付き合う。
食べ終わった後も少し話していたが、アザムは待ちくたびれたのと話疲れて夕方過ぎには寝てしまった。
そして首にかけているペンダントを開き眺めていた。そこには両親と自分と母が抱える布に包まれた赤子が写っていた。
(この写真が本当のボクの家族……)
アザムはこの部屋で一人、写真の中の『家族』失った日からの日々を思い出していた。
すると“カチッ”と鍵の開く音がして、済まなそうな顔を扉の隙間から覗かせるレイの姿があった。
「レイさん遅いじゃないか! 待ちくたびれたしジュースも全部飲んじゃった! けど、おじさんは社長さんだからボクより優先だよね」
「本当に申し訳ない。後料理を持ってきたので、扉を開いてくれませんか?」
そう言われペンダントをそのままテーブルに置くと、アザムが扉を開ける。
ワンプレートにハンバーグとパン、スープをトレイに乗せてここに戻ってきたのだ。トレイごと一度テーブルに置き向いになるように料理をセットする。
その時レイが開いたままのペンダントに気が付き、思わず手にとる。
「これはアザム君の本当の……」
レイはその本当の家族との写真の中の笑顔のアザムを見て表情が一瞬固まる。
今絶対に“抱いてはいけない”感情が……上層部の人間として、生きるためにも捨てるべき感情。
アザムは“返して欲しい”とレイに手を伸ばした。
それに気付きレイは我に返ったような感覚になる。レイに首にかけてもらうと胸元に入れる。
「けどおじさんをいつか、“おとうさん”って言える様になるまでだから。ねえ、もうお腹ぺこぺこなんだ! 食べていい?」
「ああ、遅くなって本当にごめんね。じゃあ冷めないうちに食べましょうか?」
アザムの故郷での暮らしや、学校の様な場所で英語はこれからは必要だと言われ必死に覚えた事とか。
アザムにとって話した内容は、無難で些細な事ばかりだったかも知れない。‘これから’の生活への子どもなりの気遣い。
それであっても話せば話すほど、聞けば聞くほど自分が分らなくなるレイ。それを隠し通しながらその話に付き合う。
食べ終わった後も少し話していたが、アザムは待ちくたびれたのと話疲れて夕方過ぎには寝てしまった。