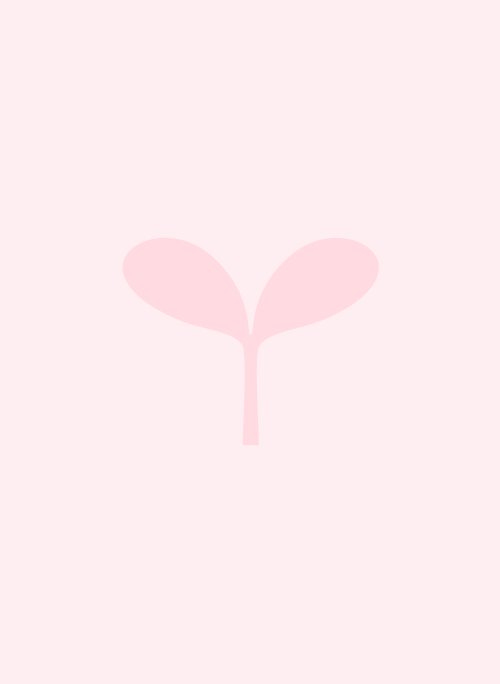【四】
もしもこの名家の令嬢の薄皮一枚でも切ってしまえば切腹は免れない。
ある意味、これも命を懸けた勝負と言えた。
それでも隼人にはこの小太刀で、少女には傷一つつけずに首に巻かれた紐のみを断ち切る自信はあった。
問題は、武芸の名家の当主が認めた恐るべき剣才を持つ娘を相手にそれができるかということだ。
幾度となく繰り返してきた稽古から、互いの剣は知っている。
頭上に雷の轟音を聞きながら、少女の繰り出してきた鋭い剣撃を目で見きって、刀を合わせずに最小の動きでかわす。
いつもながら居合いのような瞬速の剣である。
かわした瞬間に次の剣が来る。
それも、わずかに見せたこちらの隙を完璧に突いてくる。
周囲の音も、雨粒も、意識から消え失せ、ただ目の前の娘の動きを全身を目にして捉えてかわす。
それを続けながら──
改めて感嘆の思いを抱いた。
例えばあの円士郎に比べ圧倒的に膂力で劣る少女の剣速は、
男の振るう剣に比べるならば実際には決して速いとは呼べないだろう。
それでも、意識のぎりぎりでかろうじて捉えることのできるほどの瞬速に感じる。
鋭いのだ。
相手の体の体勢、位置、刀の構え、長さ。
そういったものから、どこに刀を持って行けば相手が防ぐことができないか、それを正確に読んで打ち込んでくる。
まるでどう刀を振るえばよいのかの軌跡が見えているかのように、計算し尽くされ寸分の狂いもない動きは芸術的ですらあった。
まるで鬼か天狗か──こんな完璧な剣を人間が振るえるのかと思う。
齢はまだわずか十七。
あと六年──少女が己と同じ年になった時、遙か先に追い抜かれているだろうと予感するほどの、圧倒的な才能の差を見せつけられた。
まさしく剣の精、剣の申し子と呼ぶにふさわしい娘だった。