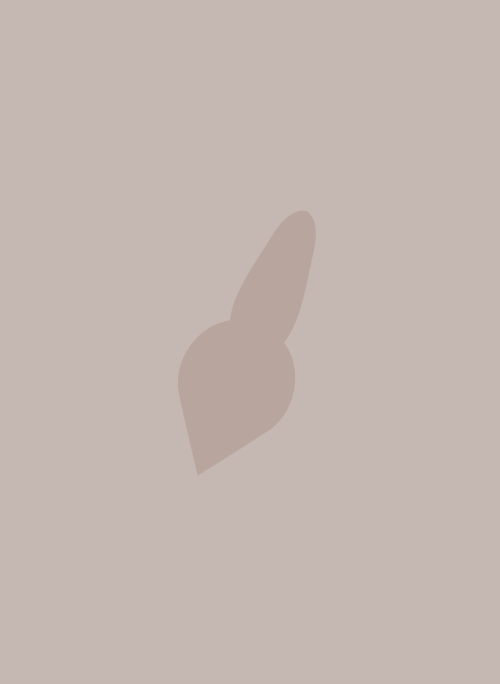「そうだね。
いつか大事な人達をこの手で守っていかなくちゃいけないからね。」
「大事な人達?」
「そう。家族・・」
アリナはなぜか泣きそうになった。
家族・・それは冷たいモノでしかなかった。
でもケイスケから聞くと、太陽のようにあたたかい気がした。
「行こっか。」
ケイスケは手をアリナに差し出した。
アリナは今度はしっかりと手を握り返した。
もう離れてしまわないようにと。
その時のアリナにはもうミウへの罪悪感はなかった。
いつか大事な人達をこの手で守っていかなくちゃいけないからね。」
「大事な人達?」
「そう。家族・・」
アリナはなぜか泣きそうになった。
家族・・それは冷たいモノでしかなかった。
でもケイスケから聞くと、太陽のようにあたたかい気がした。
「行こっか。」
ケイスケは手をアリナに差し出した。
アリナは今度はしっかりと手を握り返した。
もう離れてしまわないようにと。
その時のアリナにはもうミウへの罪悪感はなかった。