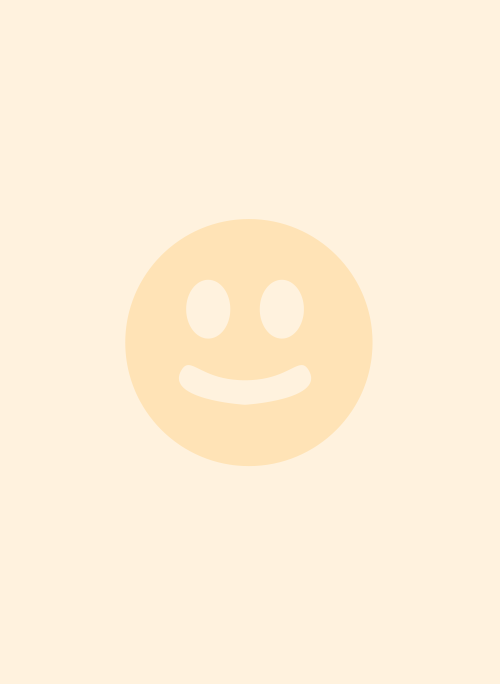帰り道は三人とも無言だった。
真里も隼人くんも、そして私も。
何も話さなかった。
駅前で真里と別れるときに。
「――覚悟、決まったらメールするから」
そう呟いた真里の一言が印象的だった。
その表情はすでに覚悟を決めたもののように見えた。
――きっと、後は時間の問題なんだね。
真里に向かって無言で頷く。
私が頷くのを確認した真里がバスに乗り込むのを見送り、私と隼人くんも電車に乗るためにホームへ向かう。
駅構内の階段を登っているとき、隼人くんがいきなり話しかけてきた。
(返事しなくて良いから、そのまま聞け)
隼人くんの方向を見るとまるで「コッチ見るな」と言わんばかりの勢いで前の方向を指差される。
仕方なく隼人くんから視線を逸らし、前を向いて歩く。
(お前が何か隠そうとしてるのは分かる。でも、大事なことなら隠さずに話してくれ)
隼人くんの言葉に思わず口を開きそうになった。
すぐさま「返事はいいから!」と一喝され、その声に思わず「ハイ!」と返事をしてしまい、周囲にいた四、五人の人から奇異の視線を浴びる羽目になってしまった。
(とにかく――だ。お前は一人ぼっちなんかじゃない。それは覚えておいてくれ)
う……その言葉に返事どころじゃなくなった。
だって――口を開いたら泣き声が出そうだ。
首を隼人くんの方向に向けたら……涙が溢れそうだ。
――私は一人ぼっちなんかじゃない。
『入れ替わった』ばかりの頃、こんな状況で苦しいのは自分一人だけだ、そんな思いをしていたのが少し懐かしいような気がする。
今は――隼人くんが居て、真里が居て、お母さんにカズちゃんも居る。
みんなが一生懸命に考えてくれて、私のためにいっぱい色んなことをしてくれて――。
みんなのその気持ちに応えるために。
私は少しでも早く『元の体に』戻ろうと思う。
――例えそれが、『元に戻ること』が……『私という人格が消える』というのと同じ意味を指しているとしても。
真里も隼人くんも、そして私も。
何も話さなかった。
駅前で真里と別れるときに。
「――覚悟、決まったらメールするから」
そう呟いた真里の一言が印象的だった。
その表情はすでに覚悟を決めたもののように見えた。
――きっと、後は時間の問題なんだね。
真里に向かって無言で頷く。
私が頷くのを確認した真里がバスに乗り込むのを見送り、私と隼人くんも電車に乗るためにホームへ向かう。
駅構内の階段を登っているとき、隼人くんがいきなり話しかけてきた。
(返事しなくて良いから、そのまま聞け)
隼人くんの方向を見るとまるで「コッチ見るな」と言わんばかりの勢いで前の方向を指差される。
仕方なく隼人くんから視線を逸らし、前を向いて歩く。
(お前が何か隠そうとしてるのは分かる。でも、大事なことなら隠さずに話してくれ)
隼人くんの言葉に思わず口を開きそうになった。
すぐさま「返事はいいから!」と一喝され、その声に思わず「ハイ!」と返事をしてしまい、周囲にいた四、五人の人から奇異の視線を浴びる羽目になってしまった。
(とにかく――だ。お前は一人ぼっちなんかじゃない。それは覚えておいてくれ)
う……その言葉に返事どころじゃなくなった。
だって――口を開いたら泣き声が出そうだ。
首を隼人くんの方向に向けたら……涙が溢れそうだ。
――私は一人ぼっちなんかじゃない。
『入れ替わった』ばかりの頃、こんな状況で苦しいのは自分一人だけだ、そんな思いをしていたのが少し懐かしいような気がする。
今は――隼人くんが居て、真里が居て、お母さんにカズちゃんも居る。
みんなが一生懸命に考えてくれて、私のためにいっぱい色んなことをしてくれて――。
みんなのその気持ちに応えるために。
私は少しでも早く『元の体に』戻ろうと思う。
――例えそれが、『元に戻ること』が……『私という人格が消える』というのと同じ意味を指しているとしても。